 労働時間
労働時間 1週間単位の変形労働時間制における時間外労働計算の注意点
1週間単位の変形労働時間制とはこの制度は、特定された週において、1日8時間、1週40時間の法定労働時間を超える労働時間を設定できますが、変形期間全体(通常は1週間)としては平均して1週40時間以内にする必要があります。ただし、この制度は、労...
 労働時間
労働時間  労働時間
労働時間 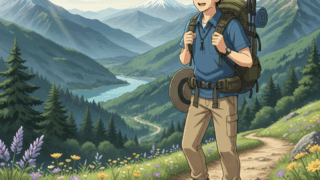 労働時間
労働時間 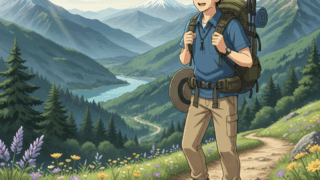 労働時間
労働時間  労働時間
労働時間  労働時間
労働時間  労働時間
労働時間  労働時間
労働時間 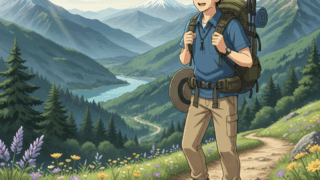 労働時間
労働時間 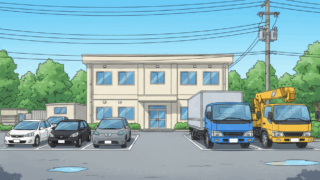 労働時間
労働時間