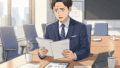労働基準法第32条4の2は、「1年単位の変形労働時間制」が適用される途中で、退職などで対象期間の途中で働き終えた人に関する、割増賃金(残業代)の精算ルールを定めています。
この条文は、特に、労働時間が「忙しい時期は長く、暇な時期は短く」設定される「変形労働時間制」の公平性を保つための規定です。
条文の解説
この条文が言っていることは、簡単に言うと次のとおりです。
対象者
1年単位の変形労働時間制を適用しているけれど、対象期間(最長1年)の途中で退職などで働くのをやめた人(労働させた期間が対象期間より短い人)。
精算が必要な条件
その人が実際に働いた期間を平均して、「1週間あたりの労働時間が40時間」を超えていた場合。
割増賃金の支払い
その「40時間を超えた部分」の労働時間について、時間外労働(残業)として扱い、割増賃金(残業代)を支払わなければならない。
注意点(計算から除く時間)
ただし、災害など臨時の必要で働かせた時間(労基法第33条)や、事前に残業として届け出て働かせた時間(労基法第36条1項、いわゆる36協定に基づく時間外労働・休日労働)は、この精算の対象となる時間から除く(それらはすでに通常の残業として処理されているはずだから)。
例で説明
変形労働時間制の「想定例」
ある会社が「1年単位の変形労働時間制」を導入し、対象期間を4月1日から翌年3月31日までの1年間と定めました。
この制度では、1年間の平均で1週間あたり40時間に収まるよう、以下の労働時間を設定しました。
- 繁忙期(4月~9月): 1週間あたり44時間
- 閑散期(10月~3月): 1週間あたり36時間
【年間平均】
(44時間×26週+36時間×26週)÷52週=40時間/週
→ 1年を通して働けば、平均40時間/週に収まるため、残業代は発生しないはずです。
対象期間の途中で退職した場合
社員Aさんが、上記制度が適用される事業場で働いていましたが、繁忙期だけ働いた後の9月30日に退職しました。
1. 労働時間の確認
Aさんが実際に働いた期間は、4月1日から9月30日までの26週間です。
- この26週間の平均労働時間は44時間/週でした。
2. 精算の計算
本来、1年間の平均が40時間/週に収まるように設計されていましたが、Aさんは途中で辞めたため、平均が40時間/週を超えてしまいました。
- 超えた時間(精算対象):
3. 割増賃金の支払い
会社は、Aさんが働いた26週間について、平均で超過した4時間/週を時間外労働(残業)とみなし、割増賃金を支払う必要があります。
- 総超過時間:
- この104時間に対し、25%以上の割増賃金を支払う必要があります。
この条文の目的
変形労働時間制は、「年間を通じてなら労働時間は公平ですよ」という前提で、特定の日や週の労働時間を長く設定できる制度です。
しかし、もし会社が意図的に労働時間が長い繁忙期に労働者を雇い、労働時間が短い閑散期に入る前に辞めさせてしまえば、会社は残業代を払わずに労働者から多くの労働力を搾取できてしまいます。
この条文は、そのような不公平を防ぐために、「途中で辞めた人については、実際に働いた期間で平均して40時間/週を超えていたら、その分は残業代を払いなさい」と定めて、労働者を保護しているのです。
条文に出てくる用語の補足
| 用語 | 意味 |
| 対象期間 | 1年単位の変形労働時間制で、労働時間を平均して週40時間以内に収めるために定めた期間(1ヵ月超え1年以内)。 |
| 前条(労基法第32条の4) | 1年単位の変形労働時間制を定める条文。 |
| 労働させた期間 | 実際にその労働者が働いた期間(退職などで対象期間より短くなることがある)。 |
| 第33条 | 災害など、やむを得ない臨時の必要により、行政官庁の許可を受けて行う時間外・休日労働。 |
| 第36条第1項 | いわゆる36協定(時間外労働・休日労働に関する労使協定)に基づき行う時間外・休日労働。 |
| 第37条 | 時間外労働や休日労働を行った場合に、割増賃金(残業代)を支払うことを定めた条文(通常25%以上、深夜や休日などはさらに割増)。 |