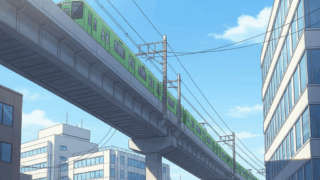 労働時間
労働時間 出張するときの移動時間は労働時間としてカウントされますか?
通常は労働時間になる通常勤務している時間帯に出張のために移動している時間は労働時間です。居眠りしていることがあるかもしれませんが、休憩時間という扱いで賃金を控除することはできません。休日等の移動は労働時間にならない場合がある移動時間が休日や...
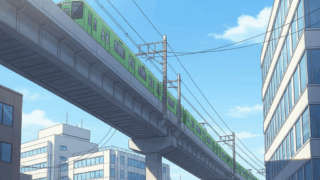 労働時間
労働時間  労働時間
労働時間  労働時間
労働時間  労働時間
労働時間  労働時間
労働時間  労働時間
労働時間  労働時間
労働時間  労働時間
労働時間  労働時間
労働時間  労働時間
労働時間