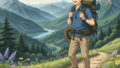労働時間把握の基本原則
フレックスタイム制においては、全員が同じ時間に出退勤する定時制とは異なり、各自の勤務時間がバラバラになるため、「遅刻・早退」の概念や時間の集計が複雑になります。
一般的に、フレックスタイム制を導入している企業が労働時間を把握するために採用している方法と、その管理のポイントについてご説明します。
前提として、フレックスタイム制であっても、会社が把握すべき情報は基本的に同じです。
- 始業時刻と終業時刻の記録
- 実労働時間(休憩時間を除いた時間)の集計
- コアタイムの勤務状況(コアタイムの遵守)の確認
採用される主な記録・管理方法
多くの企業では、従来のタイムカードではなく、より柔軟な記録・集計が可能なシステムを導入しています。
① 勤怠管理システム(クラウド型/PCアプリ)の導入
現在、最も一般的かつ効率的な方法です。
| 把握方法 | 特徴 | メリット |
| PCでの打刻 | PCやスマホの専用アプリから出勤・退勤時に打刻(GPS連携もあり)。 | 正確な時刻を記録でき、集計が自動化されるため、人事担当者の負担が劇的に軽減されます。コアタイムの打刻漏れなども自動でチェックできます。 |
| 入退室ログ | オフィスへの入退室時のカードキーの記録と連携させる。 | 物理的な証拠として機能し、実際の滞在時間を把握できます。 |
② 従来のタイムカード(紙・アナログ)を用いる場合
紙や物理的なタイムカードを使用する場合、集計や確認作業が非常に煩雑になります。
- 【課題】 カードに記録されるのは打刻時刻のみで、コアタイムの遵守状況や清算期間の総労働時間(不足/超過)は手計算でチェックする必要があり、人為的なミスが発生しやすい。
- 【対応】 タイムカードと別に、**「日々の実働時間と清算期間の残高を記載するシート」**を社員に提出させるなど、二重の管理が必要になります。
勤務管理ポイント
「遅刻」「早退」の概念がなくなる代わりに、以下の2点を厳格に管理する必要があります。
コアタイムの遵守状況の確認
フレックスタイム制において「遅刻」に相当するのは、コアタイムに間に合わない、またはコアタイム中に早退することです。
- コアタイム違反の指導: コアタイムは「必ず出勤すべき時間」として労使協定で定めた義務です。これを破った場合、遅刻・早退として扱い、厳重に指導の対象になります。
清算期間における総労働時間の把握
最も重要なのは、清算期間(最長3ヶ月)の最終日に、社員が「働くべき総労働時間」を満たしているかを確認することです。
| 状況 | 対応(システムによる自動計算) |
| 所定労働時間より不足 | 不足時間分を賃金から控除するか、翌清算期間に持ち越して労働させる(労使協定で定める必要があります)。 |
| 所定労働時間より超過 | 超過時間のうち、法定労働時間の総枠を超えた分は、時間外労働(残業)として割増賃金を支払う必要があります。 |
勤怠管理システムを導入すれば、社員自身がログインして「現在までの累積労働時間」や「目標達成までに残りの日数で必要な平均労働時間」をリアルタイムで確認できるため、社員による自己管理も促すことができます。
一般的な不足時間の処理方法
結論から言うと、「賃金控除」を採用するのが最も一般的で、労務管理上もシンプルかつ確実な方法です。
| 処理方法 | 一般的な採用度 | 特徴とメリット・デメリット |
| A. 賃金控除 | 最も一般的 | 【特徴】 不足した分の労働時間の賃金を、翌月の給与から差し引きます。 |
| 【メリット】 労働基準法の**「ノーワーク・ノーペイの原則」**に則った、最もシンプルで明確な処理方法です。賃金債権債務が翌清算期間に持ち越されず、管理が容易です。 | ||
| 【デメリット】 社員は給与が減るため、特に生活設計に影響が出やすい場合があります。 |