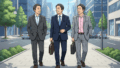従業員の方が65歳の誕生日を迎えた際の社会保険手続きは、主に介護保険料と、配偶者がいる場合の国民年金第3号被保険者の切り替え、そして年金受給と労働の調整に関わる点がポイントとなります。
介護保険(給与天引きの停止)
従業員が65歳に到達した月(誕生日の前日)から、介護保険の扱いが変わります。
| 項目 | 65歳到達による変更点 | 会社の対応 |
| 被保険者区分 | 第2号被保険者(40歳〜64歳)から第1号被保険者(65歳以上)に移行します。 | 給与からの介護保険料の控除を停止します。 |
| 保険料納付 | 65歳以降の介護保険料は、原則として市区町村が年金からの天引き(特別徴収)や納付書/口座振替(普通徴収)で本人から直接徴収します。 | 会社での徴収・納付は不要になります。 |
- 注意点: 介護保険料の控除は、65歳に到達した月(誕生日の前日がある月)の分から停止します。
厚生年金保険・健康保険(継続)
厚生年金保険と健康保険は、70歳および75歳までは引き続き加入が継続します。
| 保険の種類 | 65歳到達による変更点 | 会社の対応 |
| 厚生年金 | 原則、70歳まで引き続き加入が継続し、保険料も給与から控除されます。 | 特別な届出は不要。標準報酬月額に変更がなければ、保険料も変わりません。 |
| 健康保険 | 原則、75歳まで引き続き加入が継続します。 | 特別な届出は不要。 |
雇用保険・労災保険(継続)
雇用保険と労災保険には年齢の上限がないため、引き続き加入が継続します。
| 保険の種類 | 65歳到達による変更点 | 会社の対応 |
| 雇用保険 | 65歳以降も、加入要件を満たせば「高年齢被保険者」として加入が継続します。2020年4月以降、保険料も引き続き徴収されます。 | 特別な届出は不要。 |
| 労災保険 | すべての労働者が対象であるため、継続して加入します。 | 特別な届出は不要。 |
配偶者がいる場合(第3号被保険者の切替)
60歳未満で、従業員の扶養に入っている配偶者(国民年金第3号被保険者)がいる場合は、手続きが必要になることがあります。
- 従業員が65歳になり、老齢年金の受給権を得ると、従業員は国民年金の第2号被保険者から外れます。
- これに伴い、配偶者(60歳未満)は第3号被保険者の資格を喪失し、自分で国民年金保険料を納める第1号被保険者への切り替え手続きが必要となります。
- 手続き: 従業員の配偶者本人が、住所地の市区町村役場窓口で国民年金の手続きを行う必要があります。
- 会社の対応: 会社は、配偶者にこの変更を伝え、手続きを促すよう案内する必要があります。
年金受給と労働(在職老齢年金)
65歳以降も働きながら老齢厚生年金を受け取る場合、在職老齢年金制度の対象となります。
- 在職老齢年金とは: 給与(賞与を含む)と老齢厚生年金月額の合計が一定の基準額(2025年度は月51万円)を超えると、年金の一部が支給停止される仕組みです。
- 老齢基礎年金は、この調整の対象ではありません(全額支給されます)。
- 会社の対応: 会社が年金事務所に提出する報酬月額の届出(算定基礎届、月額変更届など)に基づき、日本年金機構が年金の支給額を決定・調整します。会社として追加の届出は不要ですが、従業員から年金に関する相談を受けた場合に、制度概要を説明できると親切です。