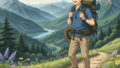商工会議所簿記検定2級に合格するためには、商業簿記と工業簿記(原価計算を含む)の知識を幅広く、かつ応用的な処理も含めて理解する必要があります。合格基準は100点満点中70点以上です。知識を習得すべき主要な項目と、理解度の目安を以下にまとめます。
商業簿記(配点:60点)
企業外部との取引を正確に記録・計算し、財務諸表を作成するための知識です。簿記検定3級の知識を土台として、より高度で実務的な論点が加わります。
| 項目 | 理解すべき内容の目安 |
| 高度な取引(債権・債務、固定資産など) | 有価証券(売買目的、満期保有目的債券、関係会社株式など)の処理、固定資産(リース取引、減価償却、圧縮記帳など)の処理、引当金(貸倒引当金、商品保証引当金、退職給付引当金など)の計上方法。これらの仕訳と決算整理を正確に行えること。 |
| 株式会社会計 | 株式の発行(新株予約権含む)、剰余金の配当、資本金・準備金の変動、株主資本等変動計算書の作成など、株式会社特有の会計処理。 |
| 本支店会計 | 本支店間取引の処理、内部利益の消去、合算財務諸表の作成プロセスを理解し、仕訳・集計ができること。 |
| 連結会計 | 資本連結(親会社の投資と子会社の資本の相殺消去)、連結修正仕訳(未実現利益の消去など)の基本的な考え方を理解し、連結財務諸表作成に必要な主要な修正仕訳を行えること。 |
| その他重要論点 | 収益認識基準に基づく処理、税効果会計(一時差異の認識と処理)、外貨建取引(為替予約など)の処理、銀行勘定調整表の作成。これらが決算整理で問われた際に、適切な仕訳・計算ができること。 |
| 決算 | 精算表または財務諸表(貸借対照表、損益計算書)を、未処理事項や決算整理事項を反映させて正確に作成できること。特に、決算整理事項(減価償却、引当金、売上原価算定など)が複雑に絡む問題に対応できること。 |
工業簿記(原価計算を含む)(配点:40点)
製造業における製品の製造原価を計算・管理するための知識です。商業簿記とは異なる、製造業特有の費用(原価)計算の流れと手法を理解することが求められます。
| 項目 | 理解すべき内容の目安 |
| 原価計算の基礎 | 費目別計算(材料費、労務費、経費の計算)、製造間接費の配賦、原価の分類(直接費・間接費、変動費・固定費)など、原価計算の全体の流れと用語を理解していること。 |
| 個別原価計算 | 注文生産を行う企業の原価計算手法。製造指図書ごとの原価を集計し、製品原価を算定できること。 |
| 総合原価計算 | 連続生産を行う企業の原価計算手法。完成品原価と期末仕掛品原価を算定できること(平均法・先入先出法)。仕損・減損が発生した場合の処理、工程別や組別の計算にも対応できること。 |
| 標準原価計算 | 標準原価を設定し、実際原価との差額(原価差異)を分析できること。特に変動費・固定費の予算差異、能率差異、価格差異などの算定と仕訳。 |
| 直接原価計算・CVP分析 | 変動費と固定費に分けて原価を計算する手法。直接原価計算による損益計算書を作成できること。CVP分析(損益分岐点売上高、目標利益達成に必要な売上高など)の計算と、経営上の意思決定への活用を理解していること。 |
合格へのポイント
- 総合的な理解と応用力: 2級では、単なる暗記ではなく、なぜその処理が必要なのかという原理原則を理解した上で、出題形式が少し変わっても対応できる応用力が重要です。
- 仕訳の徹底: 商業簿記・工業簿記ともに、すべての取引・処理について正確な仕訳ができることが基本です。特に配点の大きい第1問(仕訳)と、他の問題の土台となる決算整理仕訳は完璧を目指しましょう。
- 工業簿記の確保: 工業簿記は配点が40点と大きく、比較的出題パターンが固定化されやすいため、ここで高得点(8割以上)を確保することが合格の鍵となります。
- 時間配分: 試験時間が90分と短いため、問題を解くスピードと正確性が非常に重要です。過去問や問題集を使った反復練習で、時間内に解き切る訓練を積んでください。