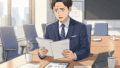本当に役立つ計画にするためのポイント
せっかく作成するのですから、単なる提出書類ではなく、社内の羅針盤として機能させるべきです。
経営計画書は、会社の規模や業種等によって異なるところもあるので、ここでは、仮に、300人規模の工作機械専門商社という設定で解説します。
経営戦略と行動計画の連動
計画を「絵に描いた餅」で終わらせないためには、戦略と現場の行動を繋げます。
- 中長期ビジョンと戦略の明確化:
- 「〇年後に売上を〇〇円にする」という目標だけでなく、そのためにどのような戦略(例:ソリューション提供型への転換、特定顧客層への深耕など)をとるのかを明確にします。
- 部門別の目標設定:
- 全社目標を、営業、技術サービス、管理などの各部門、さらに個人レベルの具体的な行動目標(KGI/KPI)に落とし込みます。300人規模であれば、組織全体でのベクトル合わせに計画書が最も役立ちます。
進捗管理の仕組みの導入
計画は作成して終わりではなく、活用してこそ意味があります。
- PDCAサイクルの組み込み:
- 計画書に記載した数値目標や行動計画の進捗を定期的に(月次など)チェックし、目標と実績の「ギャップ」を分析する仕組みを明記します。
- このギャップの原因を分析し、計画を修正・改善していくプロセスが経営計画書の最も重要な役割になります。
人材育成・組織戦略の明記
300人規模の商社にとって、人材は最大の資産です。
- 組織体制の強化:
- 今後の事業拡大に必要な人員構成、スキル、採用・育成計画を盛り込みます。特に専門商社として、技術的な知見を持つ営業・サービス人材の育成は重要な戦略項目となります。
これらの点を計画書に盛り込むことで、社内での意思統一、具体的なアクションへの落とし込みがスムーズになり、貴社の持続的な成長に大きく貢献するでしょう。
社員の力を結集する計画書
経営計画書という冊子を作ることが目標になってはいけません。せっかく作った経営計画書を実効性あるものにするためには、計画策定プロセスにおいて、トップダウンとボトムアップを組み合わせることが必要です。
理想的な計画策定プロセス:トップダウンとボトムアップの融合
経営計画は、単なる目標の「割り当て」でも「寄せ集め」でも、高い効果は得られません。全体の戦略と現場の実行力を整合させる必要があります。
トップダウン(全体戦略の提示): 会社の羅針盤
まず、経営層が以下の大枠を明確に定めます。これは、会社がどこへ向かうべきかを示す「羅針盤」の役割を果たします。
- 長期ビジョン・経営理念: 会社の最終的な目指す姿。
- 中期の全社目標(KGI): 例:3年後の売上高、利益率、マーケットシェア、資本効率など。
- 全社的な基本戦略: 目標達成のために、どの市場に注力し、何を強化するのかといった大方針。
この段階で、「工作機械専門商社として、今後どのような価値を顧客に提供していくか」という方向性を明確にし、各部門に伝えます。
ボトムアップ(実行計画の策定): 現場の知恵と具体性
トップダウンで示された大枠に基づき、各部門や個人が具体的な計画を策定します。
- 部門計画: 全社戦略(例:ソリューション提供強化)に基づき、各部門(例:営業部門、技術サービス部門)が自部門で達成すべき重要業績評価指標(KPI)と、それを達成するための具体的な行動計画を作成します。
- 個人計画: 部門KPIに基づき、個人が日々の業務の中で実行するべき具体的なアクションや目標を設定します。
このプロセスでは、現場の社員や部門責任者が持つ市場や顧客に関する具体的な知恵を計画に取り込みます。
トップダウンとボトムアップのすり合わせ(統合)
策定された部門計画や個人計画が、全社の目標や戦略と整合しているかを検証し、必要に応じて調整します。
- 現場から上がってきた計画の合計が全社目標(KGI)に満たない場合は、戦略やリソース配分を見直します。
- 現場から「この戦略では困難だ」という意見が出た場合は、経営層がその実現可能性を検討し、計画を修正します。
組み合わせるメリット
| 方式 | 特徴 | メリット | デメリット |
| トップダウン | 上層部が全て決定し、下に「割り当てる」。 | 全社的な方向性が統一される。計画策定が早い。 | 現場の納得感が薄く、実行性が低い。「やらされ感」が出やすい。 |
| ボトムアップ | 現場が計画を作り、上に「積み上げる」。 | 現場の現実的な知恵が反映され、実行性が高い。 | 全社戦略との整合性が取れず、目標が低くなりがち。 |
| 融合型 | トップが枠と目標を示し、現場が具体的計画を策定。 | 全社の統一感と現場の納得感を両立できる。 | 計画策定に時間と手間がかかる。 |
経営計画作りでは、「トップダウンとボトムアップの融合型」を採用することで、社員の参画意識を高め、目標達成へのモチベーションを向上させながら、「本当に」経営に役立つ計画を作成することができます。