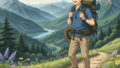賃金請求権の消滅時効について、労務・人事担当者や経理担当者向けに解説します。「だいぶ前の残業代をいま請求されてしまった」「いつまで遡って払わなければならないの?」そんな疑問にお答えします!
賃金の「請求権」とは?
労働者が、会社に対して「賃金を支払ってください」と請求できる権利を賃金請求権といいます。
これは法律上の債権ですが、一定の期間が経つと「消滅時効」によって請求できなくなることがあります。
現在の消滅時効期間は「原則5年」
労働基準法第115条(2020年4月改正)
賃金その他の請求権は、5年間行使しないときは、時効によって消滅する。
つまり、未払い給与(基本給・残業代・手当など)について、支払日から5年が経過すると請求できなくなるのです。
ただし、経過措置で、3年になっています。
改正前は「2年」、現在は「5年」!
| 区分 | 時効期間 | 備考 |
|---|---|---|
| 改正前(2020年3月まで) | 2年 | 大企業・中小企業共通 |
| 改正後(2020年4月以降) | 原則5年(当面は3年) | 附則により段階的に運用中(※詳細後述) |
⏳ 経過措置とは?なぜ「当面3年」?
実は、2020年の法改正後すぐに「5年」が完全適用されたわけではありません。
当面の間、3年とするという附則(経過措置)があります。
実務上は「2020年4月1日以降に発生した賃金請求権」について
→ 原則3年、将来的に5年へ移行予定です(段階的延長)。
時効について解説
時効は、時間の経過によって権利関係を確定させる制度です。時効制度により、長期間権利を行使しない場合、その権利が消滅したり、逆に一定期間継続して事実状態が続いている場合に権利を取得したりします。時効は、刑事事件における公訴時効と、民事事件における取得時効・消滅時効などがあります。
時効の起算点はどこから?
時効のカウントは「支払期日(支払日)」から始まります。
たとえば、
・2021年4月30日支払い予定の賃金 → その日から3年(もしくは5年)経過で時効成立
・残業代が未払いである場合も、支払期日を起点としてカウント
こんなとき「時効は止まる」
民法のルールにより、以下の場合は「時効が中断または更新」されます。
| 行為 | 効果 |
|---|---|
| 内容証明郵便による請求 | 時効が一時中断(6か月間) |
| 裁判上の請求(訴訟・調停) | 時効が中断し、勝訴で再スタート |
| 債務承認(会社が支払を認めた) | その時点から再度時効カウント開始 |
時効でも「帳簿保存」は必要!
時効で労働者が賃金請求できなくなっても、会社は帳簿を保存し続ける義務があります。
| 書類 | 保存期間 | 根拠条文 |
|---|---|---|
| 賃金台帳 | 5年間 | 労基法第109条、同施行規則第56条 |
| 労働者名簿 | 5年間 | 同上 |
| 出勤簿等 | 実務上5年 | 賃金・労働時間の裏付け資料として重要 |
企業側が気をつけるべきこと
・残業代や歩合給などの未払いリスクに備え、記録は正確に
・就業規則に「賃金請求は〇年以内に」などと定めても、時効ルールには優先されない
・過去の未払いが疑われたら、支払日と時効期間を確認
まとめ
| ポイント | 内容 |
|---|---|
| 請求できる期間 | 原則5年(当面3年) |
| 起算点 | 賃金の支払日から |
| 中断・更新 | 内容証明や訴訟、会社の承認で時効の進行が止まる |
| 記録保存 | 時効に関係なく5年間の帳簿保存が必要 |
💬 賃金の時効問題は、労使トラブルに発展しやすい分野です。
人事・労務・経理の皆さんは、「時効の知識」と「日々の記録管理」の両輪で、トラブル予防に努めましょう!