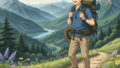労働時間を合計する
パートで働く人を中心に、複数の職場を掛け持ちで働いているひとがいます。
会社は、異なる事業場で働く人たちの労働時間を合計して把握する必要があります。
労働基準法第三十八条 労働時間は、事業場を異にする場合においても、労働時間に関する規定の適用については通算する。
この「事業場を異にする」は、「事業主を異にする場合を含む」という通達があります。
実務上の留意点
ダブルワーク労働者を把握する
まず、会社はダブルワークをしている従業員を把握しなけれればなりません。ダブルワークを禁止している会社は別として、通常はダブルワークであるかどうか、採用時に確認する必要があります。採用後にダブルワークになる場合もあるので、そのような場合は申告する必要があることを周知しておく必要があります。
申告してもらうのは、ダブルワーク先の会社名等の情報、所定労働時間等です。自社の所定労働時間とダブルワーク先の所定労働時間とを通算し、法定労働時間を超えないかどうか判断します。
労働者本人が、職場に隠して別な職場で働いていることもあると思います。その場合、会社が相当の注意を払っても知りえなかった場合には免責を主張できると思います。
会社が相当の注意を払っていなかったと認められれば、従業員が隠して働いていた場合でも、会社に責任が生じる可能性があります。
責任があるとされた場合は、割増賃金未払いに対する責任だけでなく、過重労働による健康被害等にも責任が出てくると考えられます。
なお、面倒だからと、パート勤務者のダブルワークを禁止するのは、憲法で認められた職業選択の自由に違反することになるし、生活の資を奪うことになるので無理です。
割増賃金は労働時間を足して計算する
二つの職場で働いた時間を足して、法定労働時間(1日8時間、週40時間)を超えれば、割増賃金を払わなければなりません。この場合は、法定労働時間を超えた時点で働いてた職場、原則として後の職場に割増賃金を支払う義務があります。
例えば、ある労働者が日中にA店舗で5時間、夕方からB店舗で5時間働いた場合は、5時間+5時間=10時間となり、8時間を超える時点で働いていたB店舗は2時間分については割増賃金を払わなければなりません。
ただし、午前の職場で4時間、夕方の職場で4時間の契約をしている場合は、午前の職場で超過勤務をさせれば全体として8時間を超えることが明らかなので、この場合は午前の職場に割増賃金を支払う義務があります。
上述のように後の会社というやり方の他に、労働契約の順序によるという考え方もあります。その場合、通算して法定労働時間を超えたときは、後から労働契約を締結した職場が割増賃金を負担することになります。
どちらであっても、きちんと割増賃金が支払われるのであれば問題あります。
時間外労働の上限規制に注意する
時間外労働の上限規制には、
① 延長できる限度時間(月45時間・年間360時間以内)
② 特別条項の上限(年720時間以内)
③ 1か月の労働時間を100時間未満(時間外労働と休日労働の合計)
④ 2か月ないし6か月の平均労働時間を月680時間以内(時間外労働と休日労働の合計)
という4つの上限があります。
このうち、①と②については事業場に対して適用される規制です。
つまり、その事業場で労働者が何時間働いたかが重要で、仮にある労働者が複数の事業場で働いていたとしても、その労働時間を通算して考える必要はないということです。
一方、③と④は労働者個々に適用されるので、異なる事業場同士でも労働時間を通算する必要があります。
よって、同じ月にAという事業場で月50時間、Bという事業場で月55時間働いた場合、「1か月100時間未満」の上限を超えるため法違反となります。
これらは厚生労働省のQ&Aに、転勤の際の労働時間の通算で説明されていますが、副業・兼業であっても基本的な考え方は同じと考えるべきでしょう。
労働時間通算の管理モデル
管理モデルとは
労働時間通算の基本は、上記のように、従業員が副業や兼業している場合、従業員の申告等により、それぞれの使用者が自らの事業場における労働時間と他の使用者の事業場における労働時間とを通算して管理する必要があります。
現実的には、従業員とその勤務する複数の会社との間で、日々の労働時間を報告する必要がありかなり煩雑です。
そこで、厚生労働省は、ガイドラインで、簡便な労働時間管理の方法として「管理モデル」を示しました。
関係先との合意が必要
管理モデルを実施するためには、副業・兼業を行う従業員と、副業・兼業先の事業場との合意が必要です。
従業員から副業・兼業の申し出があったさいは、以下の事項を申告させる必要があります。
□ 副業・兼業先の事業内容
□ 副業・兼業先で労働者が従事する業務内容
□ 副業・兼業先での労働時間
副業・兼業先の事業場とは以下の事項について確認する必要があります。
□ 副業・兼業先との労働契約締結日、契約期間、業務内容
□ 副業・兼業先での所定労働時間、始業・終業時刻、休日
□ 副業・兼業先での所定労働時間の有無、見込み時間数及び最大時間数
□ 副業・兼業先との連絡事項の伝達手段と窓口
管理モデル導入後
以下、従来の使用者をA社、新しい使用者をB社とします。
使用者Aでの法定外労働時間(1週40時間、1日8時間を超える労働時間)と、使用者Bでの「労働時間」を合計して、単月100時間未満、複数月平均80時間以内となるように、各々の使用者の事業場における労働時間の上限をそれぞれ設定します。
管理モデルの導入後、使用者Bは、使用者Aでの実際の労働時間にかかわらず、自らの事業場の「労働時間全部」を「法定外
労働時間」として、割増賃金を支払います。
これにより、使用者Aおよび使用者Bは副業・兼業の開始後、それぞれあらかじめ設定した労働時間の上限の範囲内で労働させる限り、他の使用者の事業場での実労働時間の把握を要することなく、労働基準法を守ることができます。