 社会保険
社会保険 従業員が65歳になったときの社会保険手続き
従業員の方が65歳の誕生日を迎えた際の社会保険手続きは、主に介護保険料と、配偶者がいる場合の国民年金第3号被保険者の切り替え、そして年金受給と労働の調整に関わる点がポイントとなります。介護保険(給与天引きの停止)従業員が65歳に到達した月(...
 社会保険
社会保険  社会保険
社会保険  社会保険
社会保険  社会保険
社会保険  社会保険
社会保険 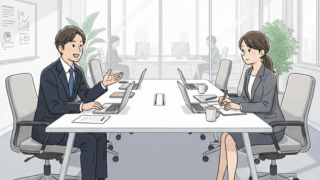 社会保険
社会保険  社会保険
社会保険  社会保険
社会保険  社会保険
社会保険  社会保険
社会保険