 労使協定
労使協定 従業員が一人の会社でも残業をさせるには労使協定が必要か
労使協定がない残業は違法ですたとえ従業員が一人の会社でも、労働基準法で原則禁止されている時間外労働をさせるのであれば労使協定(三六協定)が必要です。三六協定を結ばないまま残業をさせれば労働基準法違反になります。就業規則は10人に満たない場合...
 労使協定
労使協定  労働時間
労働時間  採用
採用  育児介護
育児介護  育児介護
育児介護 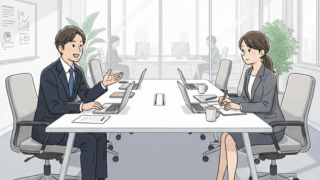 育児介護
育児介護  雇用均等・女性活躍
雇用均等・女性活躍  育児介護
育児介護  育児介護
育児介護  育児介護
育児介護