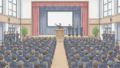起訴休職とは何か
起訴休職とは、従業員が刑事事件で起訴された場合に、会社がその従業員に就労を一時的に免除させる制度です。これは、あくまで会社が定める就業規則上の休職事由の一つであり、法律で義務付けられているものではありません。
起訴休職を定める主な目的は、以下のような事態を防ぐためです。
- 起訴された従業員をそのまま就労させた場合に、会社の社会的信用が失墜したり、顧客や取引先からの信用を損ねたりするリスク。
- 職場内で「犯罪容疑者」というレッテルを貼られることで、他の従業員との人間関係が悪化し、職場の秩序が乱れるリスク。
- 従業員が裁判対応のために労務を提供できなくなる事態に備える。
ただし、起訴されたという事実だけで直ちに解雇するのではなく、確定判決が出るまでの間、従業員の身分を保全しつつ、会社への出勤を一時的に停止させるための措置です。この制度は、会社にとっても従業員にとっても、最終的な処分の判断を慎重に行うための期間として機能します。
起訴休職の期間と賃金の扱い
休職期間
一般的には、起訴されてから判決が確定するまでと定めることが多いです。ただし、無罪判決が出た場合、その時点で休職事由が消滅したとみなし、検察官が控訴したとしても休職を継続させる根拠は失われるため、復職を命じるのが妥当です。
一方、有罪判決が出た場合でも、本人が控訴すればまだ確定判決には至っていないため、休職を継続させることになります。
休職中の賃金
休職中の賃金は、就業規則に特別の定めがない限り無給とすることが一般的です。この無給の扱いは、就業規則に明確に規定されていれば法的な問題は生じません。
起訴休職と懲戒処分
逮捕や起訴されたという事実のみをもって、直ちに懲戒処分を科すことは慎重に考える必要があります。懲戒処分は、以下の点を総合的に判断したうえで決定しなければなりません。
- 会社の受けた具体的な損害: 事件の内容や規模
- 会社の社会的信用の失墜の程度: 会社の業種や規模、事件の報道状況など
- 職場秩序への影響: 他の従業員への影響、職場の風紀の乱れなど
- 労務提供の可能性: 勾留の有無、出勤の可否
懲戒処分を下す際には、就業規則に定められた懲戒手続きに則り、慎重に審議した上で決定することが不可欠です。
有罪判決が確定した場合は、その事実が懲戒処分を科すための大きな根拠となります。ただし、この場合も就業規則に定めた懲戒の手続きを確実に実行しなければなりません。
懲戒処分が決定した場合の扱いは、以下の通りです。
- 懲戒解雇:会社が定めた解雇の手続きを経て、雇用関係を終了させます。
- 懲戒解雇以外の処分(停職、減給など):懲戒処分を科した後に、社員を職場に復帰させることになります。
就業規則への規定
起訴休職を命じるには、就業規則にその旨を定めておくことが必須です。規定がなければ、会社は起訴を理由に休職を命じることができません。
就業規則の規定例
例1: 従業員が刑事事件に関して起訴されたときは、原則として判決確定までの期間は休職を命じる。
例2: 従業員が刑事事件に関して起訴され、勾留されるなどして勤務ができないと認められるとき、または、起訴により会社の正常な業務運営に支障をきたすおそれがあるときは休職を命じる。
なお、就業規則には上記のような要点を定め、詳細は「休職規程」などに定めておくと、より詳細な運用が可能になります。
起訴休職規定を設けない場合
就業規則に起訴休職の規定がない場合でも、会社として対応は可能です。
- 勾留中の扱い:勾留されている期間は出勤できないため、欠勤扱いとすることが一般的です。有給休暇を従業員に取得させることもできますが、本人の意向を踏まえて判断します。
- 保釈後の扱い:起訴されたまま保釈された場合、会社として対応方針が固まるまでの間、短期間であれば自宅待機を命じることも可能です。この場合、賃金をどうするかについて就業規則に規定があるか確認が必要です。
起訴休職の規定がなくても、懲戒処分の要件を満たせば、会社は懲戒処分を科すことが可能です。
このような背景から、「あえて起訴休職を設けなくても対応できる」という考え方に基づき、起訴休職を定めていない会社も多く見られます。しかし、起訴された従業員を会社としてどう扱うか、事前に明確なルールを定めておくことは、労使間のトラブルを未然に防ぐ上で非常に重要です。