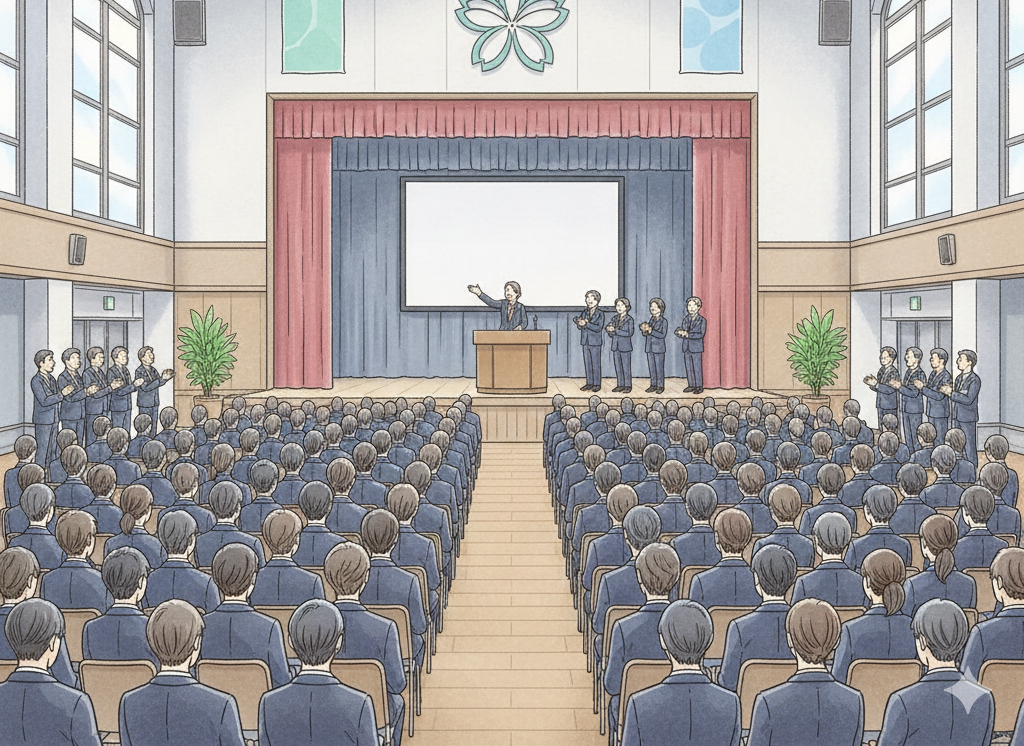経営方針発表会の意義
経営計画を作っている会社では、毎年、策定した経営計画を公式に発表する機会を持つことが多いです。これは、経営方針発表会や経営計画発表会と呼ばれるものです。
発表会を恒例行事にする
経営計画発表会を単なる会議ではなく、全社で目標達成に向けて一致団結する恒例行事と位置づけます。
- 社長の直接的なメッセージ:会社のビジョンと、今期の目標に込めた「想い」や「覚悟」を、社長が熱意をもって社員に直接語りかけます。
- 部門代表者による「コミットメント」:各部門長や部門の若手代表などが登壇し、全社目標達成に向けた部門計画や具体的な行動目標(KPI)を発表し、コミットメント(誓い)を表明する場を設けます。これは、単なる割り当てではなく「自分たちの計画」であることを意識づける効果があります。
- 質疑応答・意見交換:質疑応答の時間を設け、社員の疑問をその場で解消します。質問の機会を提供することで、社員が計画を「自分事」として考えるきっかけを与えます。
できれば年度末にも開催する
年に一度、発表会のなかで前年の振り返りも兼ねるのが一般的ですが、できれば、年度末に結果報告と、貢献者を称賛する場を用意しましょう。
- 成功事例の共有と表彰:計画達成に貢献した部門や個人を表彰し、具体的な成功事例(プロセス)を発表してもらいます。これは、他の社員の行動の模範となり、計画の実現方法を社内に浸透させる効果があります。
- 「計画と実績のギャップ」の分析:計画が未達だった場合も、それを責める場ではなく、「なぜギャップが生じたのか」「来期どう改善するか」を前向きに議論する場とします。
経営方針は、各部門の計画をもとに策定するので、それぞれの部門は自部門の計画内容を承知しています。そのため、会社全体としてまとまった経営方針は、資料として配布すればよいことで、あえて、経営方針発表会という形式ばった行事をする意味がないという意見もあります。
しかし、自分の目標数字を知っていればよい、配付された資料を読めばよい、という考えでは計画達成に向けて従業員の力を十分に引き出すことはできません。従業員が経営方針の作成と実践の重要性は、多少大げさな行事を準備し実施することで、従業員の目と耳、心に訴える効果が期待できるのです。
このため、なるべく非日常的な舞台を用意するために、ホテル等の宴会場を借りて行うのが一般的です。
誰に向けた経営方針発表会か
経営方針発表会の主役を取引先にするか、従業員にするかでやり方が異なります。
取引先に向けた経営方針発表会
この場合は、取引先への協力要請が主目的になります。
会社の成長のためには取引先の協力が不可欠です。特に、資本の提供者である主要な仕入先や金融機関は重要です。取引先は、今後どのような経営をしていくのか、具体的な展望に関心を持っています。したがって、来年以降の数値目標はもちろん、その数値目標を達成するための具体的な手段を示す必要があります。
また、過去年度の計画の達成状況や成長度合いにも大きな関心を持っています。したがって、前年度の計画の実行状況、業績についての説明が重要です。前年も開催している場合は、前年計画した内容がどうなったのか、きちんと分析をつけて説明することが信頼を得ることができます。
なお、取引先を対象にした経営方針発表会は、説明だけで終わないのが一般的です。せっかく足を運んでもらうのですから、説明のあとに、懇親会、観光、ゴルフなどをセットして接待的な要素を加えます。
従業員に向けた経営方針発表会
従業員を対象にする場合は、策定した経営理念、経営方針を従業員に周知するとともに、団結心を醸成する効果を狙うものにします。
したがって、なるべく多くの従業員が参加できるように工夫する必要があります。
発表会の準備
経営計画書
経営方針を記載した経営計画書を製本しましょう。幹部社員向けのものは、表紙に社外秘の表示をし、配布リストをつくり、配布NOを表示します。部外秘であることを認識させましょう。また、配布しっぱなしではなく、会議の度に持参させ活用することも大事です。
一般従業員向けのものは、幹部従業員向けの要約版にします。
取引先等に配布するものは、対外的に周知を図りたい部分をピックアップして、分かりやすいように写真や図などを加えてつくります。
経営方針発表会の時間配分
発表会の時間は、内容によりますが、長くても2時間くらいです。一例としては、午後3時に開始し、5時くらいに懇親会に移行するとよいでしょう。
経営方針発表会の次第例
□ 開会のあいさつ
□ 来賓紹介
□ 社長の経営方針発表
□ 各部門管理者の部門経営計画発表
□ 閉会のあいさつ
ウェブ開催
経営計画の浸透と社員の参画意識向上において、キックオフ(スタート時)と振り返り(終了時)の全体イベントは非常に重要です。できれば全員参加にしたいものですが、会社の規模や業種によっては、物理的な集結が難しいかもしれません。その場合は、以下のようなハイブリッド形式を検討できます。
- 主要な役員・管理職は対面: 幹部層は一堂に会し、発表や議論の熱量を最大化します。
- 一般社員はウェブ参加または地域ごとの集合: 各拠点や支店に集まってもらい、大型スクリーンで中継を視聴させ、視聴後に拠点内でディスカッションを行う場を設けるなど、双方向性を担保する工夫を盛り込みます。
注意点
一部をウェブ参加する場合は次の点に留意しましょう。
- 一方通行の情報伝達になりがち:ウェブ中継は情報の「周知」には有効ですが、社員は基本的に傍観者となってしまいます。質問や意見交換が十分に行われず、「やらされ感」や「他人事」になりやすいです。
- 熱量・感情の伝達が難しい:経営トップの**「決意」「覚悟」「ビジョンへの熱意」**は、直接対面で語りかけるからこそ伝わり、社員のモチベーションに火をつけます。画面越しでは、その熱量が薄れてしまいがちです。
- 一体感の醸成が難しい:同じ場所に集まることで生まれる、「同じ目標に向かって進む仲間である」という一体感や高揚感は、オンラインでは得られにくい要素です。これは特に年度初めの「キックオフ」において重要な要素です。