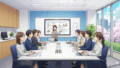今回は「職務給(しょくむきゅう)」という給与制度について、わかりやすく解説します。聞いたことはあるけど、よく知らないな…という方も多いのではないでしょうか。実は、日本でも最近注目されているこの制度。海外ではどうなっているのか、その実態も見ていきましょう。
職務給ってなに?
職務給とは、「仕事の内容(職務)の価値」に基づいて賃金を決定する給与制度です。
簡単に言うと、「誰がその仕事をするか」ではなく、「その仕事そのものの難易度や責任の重さ」で給料が決まります。
年功序列制度では、年齢や勤続年数が上がるにつれて給料も上がりますが、職務給はそうではありません。もし20代の若手社員でも、ベテラン社員と同じ難易度の責任ある仕事を任されれば、同じ給料になる可能性があるということです。
この制度を導入するためには、まず社内のすべての仕事を洗い出し、それぞれの「職務の価値」を評価する必要があります。これを「職務評価」と呼びます。
職務給のメリット・デメリット
この制度には、以下のようなメリットとデメリットがあります。
- メリット
- 評価基準が明確: 何をすれば給料が上がるのかがわかりやすいです。
- 同一労働同一賃金: 同じ仕事なら同じ給料になるため、不公平感が少なくなります。
- 生産性の向上: 難しい仕事や責任ある仕事に意欲的に取り組む社員が増える可能性があります。
- デメリット
- 導入・運用が大変: 職務評価を行う手間やコストがかかります。
- 配置転換が困難な場合も: 職務内容が変わると給料も変わるため、社員が異動を嫌がるケースもあります。
- 年功序列からの移行が難しい: これまでの給与水準を維持しつつ職務給に切り替えるのは、非常に複雑な調整が必要です。
海外では職務給が主流って本当?
結論から言うと、本当です。特に欧米では、職務給が一般的な給与制度として広く浸透しています。
なぜ海外で職務給が主流になったのでしょうか?そこには、労働市場の考え方の違いが大きく関わっています。
欧米では、個々の労働者が専門的なスキルを持ち、そのスキルを活かせる職務に就くのが一般的です。企業は、その職務を遂行できる人材を市場から採用します。そのため、「この職務にはこれくらいの価値があるから、これくらいの給料を払う」という考え方が自然に根付いています。
どのように運用されているの?
海外の多くの企業では、「ジョブディスクリプション(職務記述書)」というものが作成されています。
これは、仕事の内容、必要なスキル、責任範囲などを詳細に記した書類です。採用時には、このジョブディスクリプションを公開し、それに合った人材を募集します。社員は、このジョブディスクリプションに沿って仕事を行い、評価もこれに基づいて行われるのが一般的です。
多くの企業で、職務給の考え方が基本になっています。エンジニア、マーケティング担当者、人事など、それぞれの職務に対して市場価値を考慮した給与が設定されています。
職務給における「経験」の評価
欧米では、運転職や機械オペレーターなどの職種にも職務給が適用されるのが一般的です。これらの職務は、特定のスキルやライセンス、そして責任範囲が明確であるため、職務給制度と非常に相性が良いのです。
しかし、「経験年齢問わず同じ給料になるか」というと、厳密にはそうではありません。
職務給はあくまで「職務の価値」に基づいていますが、その職務を遂行する個人の「熟練度」や「習熟度」も評価対象となります。これは、同じ「大型トラック運転手」という職務でも、経験の有無によってパフォーマンスや責任の度合いが変わるからです。
具体的な評価基準の一例を挙げると、以下のようになります。
1. 職務のレベル分け
同じ「大型トラック運転手」でも、以下のように職務のレベルを細分化することがあります。
- 初級: 入社したばかりで、短距離・定型ルートの運転が主な業務。
- 中級: 複数のルートを担当し、特定の種類の荷物の取り扱いも可能。
- 上級: 危険物や特殊な荷物、または長距離・国際ルートを担当し、高度な判断が求められる。
2. 評価基準
それぞれのレベルで、以下の項目を評価します。
- 安全運転記録: 事故歴や違反歴の有無。
- 効率性: 決められた時間内にどれだけ正確に業務をこなせるか。
- 専門性: 危険物取扱者など、追加で取得した専門資格。
- 顧客対応: 荷主や顧客とのコミュニケーションスキル。
3. 給与体系
これらの評価に基づいて、給与が設定されます。例えば、以下のようになります。
- 基本給: 「大型トラック運転手」という職務に設定されたベースの給料。経験年数に関係なく、この基本給は共通です。
- 手当・ボーナス: 危険物手当、長距離手当、無事故ボーナスなどが加算されます。これらの手当は、個人の熟練度や担当する業務内容によって変動します。
- 昇進: 一定の経験や実績を積むことで、より責任の重い「上級運転手」などの職務に昇進し、給与が引き上げられます。
このように、海外の職務給制度では、「職務」をベースにしながらも、個人の「スキル」や「経験」を評価する仕組みが組み込まれているのが一般的です。これにより、単なる年功序列ではなく、個人の能力や貢献度を適正に評価する運用がなされています。
なぜ同じ職務でも給与に差がつくのか?
以上のように、職務給は「同じ仕事をすれば同じ給料」という単純なものではなく、「同じ職務に就いている人でも、その貢献度や習熟度に応じて給与に差がつく」のが現実の運用です。
それは、同じ職務であっても、社員一人ひとりが生み出す価値や責任の果たし方が異なるからです。
例えば、経験の浅い若手とベテランでは、以下のような違いが生まれます。
- ベテランの貢献:
- 新人や後輩の指導・育成
- 予期せぬトラブルへの対応
- 業務プロセスの改善提案
これらの付加価値は、単に「仕事をこなす」という範囲を超えた、組織への重要な貢献と見なされます。そのため、同じ「職務」でも、より高い責任を負ったり、より複雑な業務をこなしたりする社員には、それに応じた高い報酬が支払われます。
このことから、多くの職務給制度は、「職務」そのものの価値と、その職務を遂行する個人の能力や貢献度を組み合わせたハイブリッドな評価体系を採用していると言えます。
つまり、基本となる給与は職務によって決まりますが、そこに個人の実績やスキル、行動を評価する手当やボーナス、昇進といった要素が加わることで、公平性と個人の努力を両立させているのです。
職務給は、「あなたが担う仕事にはこれだけの価値があります。その上で、あなたのパフォーマンスが優れていれば、さらに報います」というメッセージを社員に伝える制度とも言えます。
職能給になると自分の業務範囲を超えて仕事をしなくなる?
職務給制度は、業務範囲が明確になるため、従業員が自分の担当外の仕事を避ける傾向にあると言われています。この現象は「サイロ化」や「セクショナリズム」と呼ばれ、職務給制度のデメリットの一つとして認識されています。
- 評価基準の明確化: 職務給は、あらかじめ定められた職務記述書(ジョブディスクリプション)に基づいて給与や評価が決まります。従業員は、自身の評価を上げるために、この職務記述書に書かれた範囲の業務に集中しようとします。
- インセンティブの欠如: 自分の業務範囲外の仕事を手伝っても、それが自身の給与や昇進に直接的に反映されることが少ないため、積極的に取り組む動機が働きにくいです。
- 責任範囲の明確化: 職務給では、各々の役割と責任が厳格に定義されます。これにより、自分の業務で発生した問題には責任を持つ一方で、他部署や他者の業務には関与しなくなることがあります。
この問題への対策
このデメリットを克服するために、多くの企業が職務給制度に以下の工夫を加えています。
- 職務評価の柔軟性: 職務記述書に「その他、状況に応じて発生する業務」といった項目を含めたり、定期的に職務内容を見直したりすることで、制度の柔軟性を高めます。
- 「職務」と「行動」の両面評価: 職務遂行能力だけでなく、「チームワーク」「他者への協力」「改善提案」といった職務範囲を超える行動を評価する項目を評価制度に組み込み、報酬に反映させます。
- インセンティブの導入: 部署間の協力を促すためのチームボーナスや、全社的な目標達成に対する賞与を設けることで、従業員が自分の職務範囲を超えて協力する動機付けを行います。
このように、職務給制度は業務範囲が明確になるメリットがある一方で、従業員が自身の役割に固執してしまうリスクも持ち合わせています。この課題に対処するため、多くの企業は評価制度を工夫し、協力的な文化を維持しようと努めています。
日本での職務給のこれから
日本では、これまで年功序列制度が主流でしたが、グローバル化や働き方の多様化に伴い、職務給への関心が高まっています。しかし、完全に移行するのは簡単ではありません。多くの企業が、年功序列と職務給を組み合わせた「ハイブリッド型」の給与制度を模索しているのが現状です。