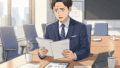有期雇用契約の従業員には、契約期間満了が来たら契約を更新しなければいい。もし、貴社でこのように考えている方がいるとしたら、それは大きなリスクを抱えているかもしれません。有期雇用契約の「雇い止め」は、無期雇用契約の解雇と同様、安易に行うとトラブルに発展し、企業側に大きな不利益をもたらす可能性があります。
雇い止めとは
有期労働契約は、期間が満了すれば当然に退職になるのが一般的ルールです。当初の契約が終了するのですから、解雇という問題は発生せず、自然に退職になります。これを「雇い止め」といいます。
雇止めをするためには、まず雇用契約を締結する段階で、契約更新に関する事項が明示されていなければなりません。
契約更新についての記載例
□ 自動更新する
□ 更新することがある
□ 契約の更新はしない
「更新することがある」という契約であれば、どういう基準で決めるのかを明示しなければなりません。
記載例
□ 契約期間満了時の業務量により判断する
□ 労働者の勤務成績、態度により判断する
□ 労働者の能力により判断する
□ 会社の経営状況により判断する
□ 従事している業務の進捗状況により判断する
等
労働契約法 第19条:雇い止め法理の適用に注意!
条文
労働契約法第十九条 有期労働契約であって次の各号のいずれかに該当するものの契約期間が満了する日までの間に労働者が当該有期労働契約の更新の申込みをした場合又は当該契約期間の満了後遅滞なく有期労働契約の締結の申込みをした場合であって、使用者が当該申込みを拒絶することが、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められないときは、使用者は、従前の有期労働契約の内容である労働条件と同一の労働条件で当該申込みを承諾したものとみなす。
一 当該有期労働契約が過去に反復して更新されたことがあるものであって、その契約期間の満了時に当該有期労働契約を更新しないことにより当該有期労働契約を終了させることが、期間の定めのない労働契約を締結している労働者に解雇の意思表示をすることにより当該期間の定めのない労働契約を終了させることと社会通念上同視できると認められること。
二 当該労働者において当該有期労働契約の契約期間の満了時に当該有期労働契約が更新されるものと期待することについて合理的な理由があるものであると認められること。
解説
この条文は、通称「雇い止め法理」と呼ばれ、有期雇用契約であっても、実質的に無期雇用契約と変わらないような状況にある場合、企業は簡単に雇い止めができないことを定めています。具体的には、以下のいずれかに該当する場合に、雇い止めが制限されます。
「期待権」が発生している場合(第19条第1号)
過去に何度も契約更新を繰り返しており、労働者が「次の契約も更新されるだろう」と合理的に期待することが認められる場合です。例えば、自動更新規定がある、更新を前提とした説明があった、更新手続きが形骸化しているなどのケースが該当します。
「客観的合理的な理由」と「社会通念上の相当性」がない場合(第19条第2号)
契約更新の拒絶(雇い止め)に、客観的に見て合理的な理由がなく、社会通念上も相当ではないと判断される場合です。これは、無期雇用契約の解雇権濫用法理とほぼ同じ考え方です。
注意すべきポイント
1.「期待権」発生の具体的なケース
・何度も契約更新が繰り返され、長期間雇用が継続していると、実質的に期間の定めのない契約と変わらないと判断されやすくなります。
・臨時的な業務ではなく、正社員と同様の恒常的な業務に従事していた場合。
・契約更新の際に面談や説明がほとんどなく、形式的に契約書にサインするだけなど、更新手続きが実態を伴っていない場合。
・同様の地位にある他の労働者が、基本的に雇い止めされることなく更新され続けている場合。
・「これからもよろしく」「長期で働いてほしい」などの期待させる言動があった場合。
・契約書に更新の上限が明記されておらず、労働者が無期限に更新されると期待するのが自然であった場合。
・業務が継続的に存在し、その業務に労働者が不可欠であった場合。
2.更新の有無、判断基準の明確化
契約書に「更新の可能性あり」「更新しない場合がある」などと明記するだけでなく、更新の判断基準も具体的に示し、労使双方で認識を共有しておくことが重要です。
3.雇い止め理由の明確化
雇い止めを行う場合は、その理由を明確にし、客観的に合理的な理由であることを証明できるよう準備しておく必要があります。単に「契約期間満了だから」という理由だけでは不十分です。
客観的に合理的な理由としては、以下のようなものが挙げられます。
・事業の縮小や廃止、経営難など、使用者側のやむを得ない事情。
・労働者の職務怠慢、勤務態度不良(無断欠勤・遅刻の繰り返しなど)、不正行為、能力不足など、労働者側に原因がある場合。ただし、これらの理由が客観的な証拠に基づき、十分に警告や指導が行われていたかどうかも判断要素となります。
・担当業務が終了したこと。
労働契約法第18条:無期転換ルール!
条文
労働契約法第十八条(抜粋) 同一の使用者との間で締結された二以上の有期労働契約の契約期間を通算した期間が五年を超える労働者が、当該使用者に対し、現に締結している有期労働契約の契約期間が満了する日までの間に、当該満了する日の翌日から労務が提供される期間の定めのない労働契約の締結の申込みをしたときは、使用者は当該申込みを承諾したものとみなす。
解説
有期労働契約が繰り返し更新され、その通算契約期間が5年を超える労働者は、現に締結している有期労働契約の契約期間が満了する日までの間に、使用者に対し、期間の定めのない労働契約(無期労働契約)への転換の申込みをすることができます。この申込みがあった場合、使用者はその申込みを承諾したものとみなされ、無期労働契約が成立します。
注意すべきポイント
1.通算契約期間の管理: 契約期間が満了した日と次の契約開始日の間に「空白期間」がある場合でも、その空白期間が6ヶ月未満であれば、通算契約期間は継続して計算されます。
2.無期転換後の労働条件は、原則としてそれまでの有期労働契約の内容(契約期間を除く)と同一となります。ただし、別途の定めがある場合はその内容によります。無期転換後の労働条件をあらかじめ就業規則等で定めておくことが望ましいでしょう。
労働基準法 第20条:解雇予告の手続き準用!
条文
労働基準法 第20条(抜粋) 使用者は、労働者を解雇しようとする場合においては、少なくとも三十日前にその予告をしなければならない。三十日前に予告をしない使用者は、三十日分以上の平均賃金を支払わなければならない。
解説
労働基準法第20条は「解雇予告」に関する条文ですが、有期雇用契約の雇い止めにおいても、一定の条件を満たす場合にはこの規定が準用されます。
具体的には、厚生労働省の「有期労働契約の締結、更新及び雇止めに関する基準」において、以下のケースでは、雇い止めの際にも解雇予告と同様に30日前までの予告、または30日分の平均賃金(解雇予告手当)の支払いが必要とされています。
・契約を3回以上更新している場合
・1年を超えて継続勤務している場合
注意すべきポイント
1.「雇い止め予告通知書」の活用: 上記の条件に該当する有期雇用労働者を雇い止めする際には、契約期間満了の30日前までに「雇い止め予告通知書」を交付するなどして、書面で通知することがトラブル回避に繋がります。
2・解雇予告手当の準備: 30日前までに予告ができない場合は、解雇予告手当の支払いが必要です。
労働契約法 第17条:契約期間中の解除は「やむを得ない事由」が必要!
条文
労働契約法第十七条 使用者は、期間の定めのある労働契約(以下この章において「有期労働契約」という。)について、やむを得ない事由がある場合でなければ、その契約期間が満了するまでの間において、労働者を解雇することができない。
解説
この条文は、有期雇用契約の期間中に契約を解除(解雇)することの厳しさを示しています。有期雇用契約は、原則として契約期間中は労使双方に契約を遵守する義務があります。
そのため、契約期間中に企業側から一方的に解雇するには、「やむを得ない事由」が必要とされています。これは、無期雇用契約の解雇よりも厳しい要件とされています。
注意すべきポイント
1.期間途中での解雇は極めて困難: 契約期間中の解雇は、例えば、従業員が逮捕・勾留された、会社の信用を著しく毀損する行為を行ったなど、極めて重大な事由がない限り認められにくいと認識しておくべきです。
2.安易な契約期間の設定を避ける: 契約期間を長く設定しすぎると、期間中に問題が発生した場合に身動きが取れなくなる可能性があります。職務内容や事業計画に応じて、適切な契約期間を設定することが重要です。
就業規則:雇い止めに関する規程等の整備!
就業規則の明確な規定は、雇い止めを適切に行う上で非常に重要です。
注意すべきポイント
1.雇い止めの事由: どのような場合に雇い止めを行う可能性があるのか(例:事業の縮小、担当業務の消滅、能力不足、勤務態度不良、更新の判断基準に満たない場合など)を具体的に定めておく。
2.更新の有無、判断基準: 契約更新の有無、更新の回数の上限、更新の判断基準などを明記する。
3.雇い止め予告: 労働基準法第20条の準用を踏まえ、雇い止めの予告に関する手続きを規定する。
就業規則にこれらの事項を明確に規定し、従業員に周知徹底することで、不要な誤解やトラブルを未然に防ぐことができます。
雇止め理由証明書
雇止めに際して、労働者から更新拒否の理由について証明書を請求されたときには遅滞なく交付しなければなりません。これは、雇い止め後に請求された場合も同じです。なお、労基法第22条の退職証明とは別のものです。
この告示について発出された通達、「有期労働契約の締結、更新及び雇止めに関する基準 (通達)平 20.1.23基発第 0123005号」には、これに記載する「雇止めの理由」は、 単に「契約期間が満了したため」ではならないとしています。
例えば、として次のような例をあげています。
□ 前回の契約更新時に、 本契約を更新しないことが合意されていたため
□ 契約締結当初から、 更新回数の上限を設けており、 本契約は当該上限に係るものであるため
□ 担当していた業務が終了・中止したため
□ 事業縮小のため
□ 業務を遂行する能力が十分ではないと認められるため
□ 職務命令に対する違反行為を行ったこと、 無断欠勤をしたこと等勤務不良のため
等
雇い止めが無効かどうかは誰が判断するのか?
雇い止めが無効かどうかは、最終的には裁判所が判断します。
労働者と使用者間で雇い止めについて争いが生じた場合、まず話し合いや労働局によるあっせん、労働審判などの手続きがとられることがあります。
しかし、これらの手続きで解決に至らない場合は、労働者が雇い止めの無効を主張して、地位確認(雇用契約が継続していることの確認)や賃金支払いを求めて裁判を起こすことになります。
裁判所は、上記の「雇い止め法理」に基づき、個別の事案における様々な事情(契約更新の回数や通算期間、業務内容、使用者側の言動、更新手続きの実態、雇い止めの理由など)を総合的に考慮して、雇い止めが客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められるかどうかを判断します。
雇止めが無効とされた場合、ただちに無期契約に転換になるのではありません。従前と同一の労働条件で、有期労働契約が更新されたことになります。
まとめ
有期雇用契約の雇い止めは、単に契約期間満了だからといって簡単にできるものではありません。労働契約法第19条の「雇い止め法理」、労働基準法第20条の「解雇予告の準用」は特に重要なポイントです。
雇い止めを行う際は、以下の点を改めて確認し、慎重に進めましょう。
1.雇い止めの正当な理由があるか?(客観的合理性、社会通念上の相当性)
2.労働者に期待権が発生していないか?
3.30日前までの雇い止め予告(または解雇予告手当の支払い)は適切に行ったか?
4.契約期間中の解雇ではないか?(やむを得ない事由があるか)
5.雇い止めに関する規定が就業規則に明確に整備され、周知されているか?
これらの注意点を踏まえ、適切な手続きを踏むことで、企業は法的リスクを最小限に抑え、健全な労使関係を維持することができます。ご不明な点があれば、専門家(弁護士、社会保険労務士など)に相談することをおすすめします。