 育児介護
育児介護 産後パパ育休取得者に出生時育児休業給付金が支給される
出生時育児休業給付金とは産後パパ育休と練度する制度です。令和4年10月1日より施行されています。産後パパ育休(出生時育児休業)を取得取得する場合、その間は休業していることから会社から賃金の支払いを受けることができません。その間の所得補填とし...
 育児介護
育児介護  育児介護
育児介護 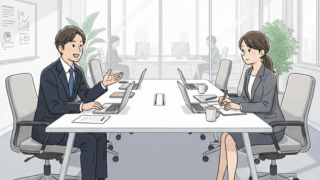 育児介護
育児介護  雇用均等・女性活躍
雇用均等・女性活躍  育児介護
育児介護  育児介護
育児介護  育児介護
育児介護  安全衛生管理
安全衛生管理 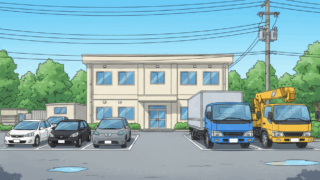 労働時間
労働時間  健康保険
健康保険