 ハラスメント
ハラスメント 私の部下の言動がパワハラだと言われましたが、当人に悪気がありません。どう対応すればよいでしょうか?
メーカーの営業課長です。部下に元気で声が大きい者がいます。多少他人に対する配慮に欠ける言動もありますが、仕事はきちんとやっています。その者の言動がパワハラだという声が複数あり、上司として対応に困っています。これまでも注意したことはあるのです...
 ハラスメント
ハラスメント  ハラスメント
ハラスメント  ハラスメント
ハラスメント  ハラスメント
ハラスメント  ハラスメント
ハラスメント  ハラスメント
ハラスメント  ハラスメント
ハラスメント  ハラスメント
ハラスメント  ハラスメント
ハラスメント 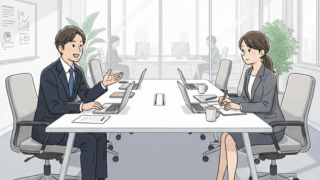 ハラスメント
ハラスメント