 労働時間
労働時間 退職するとき、有給休暇は消化できる?買い取ってもらえる?
有給休暇取得を拒むことはできません退職前に残っている有給休暇を全部使いたい、という申し出を受けることがあります。退職の意思表示と同時に、明日から有給休暇を使うのでもう出てきません、などと言われることもあります。会社としては最低限の引継ぎくら...
 労働時間
労働時間 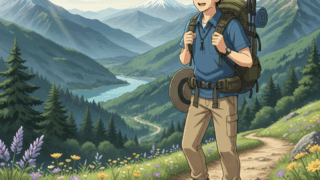 労働時間
労働時間  労働時間
労働時間 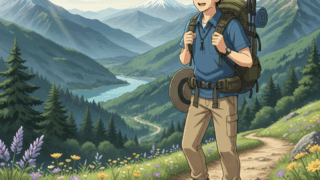 労働時間
労働時間  労働時間
労働時間 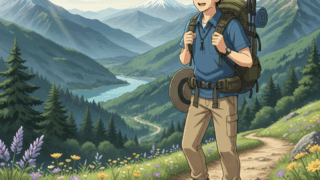 労働時間
労働時間  労働時間
労働時間  労働時間
労働時間  労働時間
労働時間  労働時間
労働時間