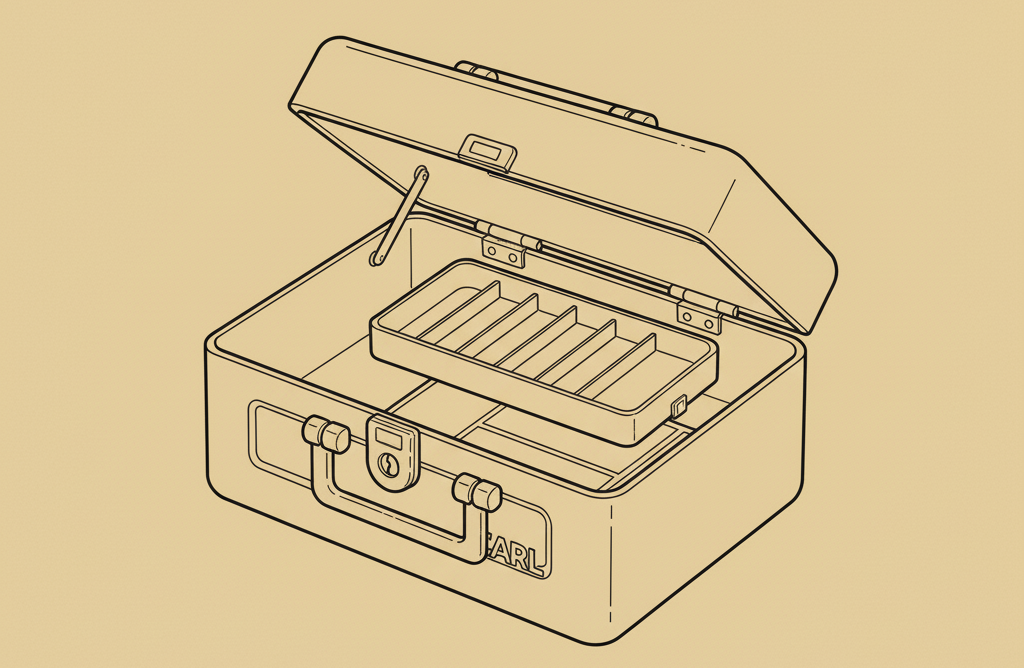退職金とは
退職金とは退職する従業員に支給される金銭です。一時金で支給されるのが一般的ですが、年金方式による支給もあります。
法律で退職金を払わなければならないと決められているわけではありません。仮に退職金制度がなくても法的な問題はありません。
ただし、就業規則等で退職金を支払う制度を定めている場合は、その退職金は労働基準法11条に定める賃金として扱われるので、制度で定めた支給額は必ず支払わなければなりません。
また、就業規則に退職金についての定めがなくても、退職時に手当等を支払うことが慣例的に行われている場合は、労使慣行が成立していることになるので、支払義務があります。就業規則に書いていないからといって勝手にやめることはできません。
退職金の支給理由
法律で義務付けられていませんが、多くの会社では退職金を支給しています。
横並び意識
すでに多くの会社に退職金制度があることが、新たに創業される会社も退職金制度を作る動機になっています。福利厚生の一つとされているので、退職金制度が無い会社は待遇面で見劣りするという考え方です。
生活保障の意味合い
多くの従業員は定年退職をするときにはすでに老後にさしかかる年齢になっています。終身雇用という言葉があるように、同じ会社に長い間勤務してきた従業員に、定年後の生活を支える一時金を支給するのが会社の責務だという考え方です。
功労金という考え方
これまでの勤務における会社に対する貢献は、これまでに受け取った賃金の総額を上回っていると考えて、賃金で報いきれなかった分を退職時に支給するという考え方です。
賃金の後払い
若いうちは低めに設定された賃金で働き、退職のときに低かった分を清算するという考え方です。
退職抑制のねらい
長く勤務するほど退職金が増えるので、従業員に早期の退職を思いとどまらせ、長く勤務してもらえるという考え方です。特に、自己都合退職と定年退職で支給額に差をつけたり、勤続年数が一定年数を超えるまでは退職金額を低く抑えたりする金額設計はこの考え方に基づいています。
退職金制度のいろいろ
社内積立方式
中小企業では、退職金の原資を社内積立(社内準備)で準備している会社は依然として多く、主要な準備形態の一つとなっています。
ただし、近年は「外部積立型」の制度と組み合わせて利用する企業も増えています。
中小企業の退職金制度の準備形態
厚生労働省などの調査によると、「退職一時金制度」を導入している企業について、その支払い原資の準備形態を見ると、特に中小企業(従業員規模100人〜299人など)では、以下のようになっています。
| 準備形態 | 企業割合(複数回答) | 特徴 |
| 社内準備(内部積立型) | 56%〜65%程度 | 会社が社内で資金を積み立てる、または特に積立を行わず、退職時に会社の資金で支払う形態。中小企業で最も多く採用されています。 |
| 中小企業退職金共済制度(中退共) | 42%〜48%程度 | 国が運営する外部積立型の共済制度。税制優遇や国からの助成があり、近年導入が増加傾向にあります。 |
| 特定退職金共済制度(特退共) | 7%〜9%程度 | 商工会議所などが運営する外部積立型の共済制度。 |
※出典:東京都「中小企業の賃金・退職金事情」、厚生労働省「就労条件総合調査」など(調査年により数値は変動します)。
社内積立が多い理由と課題
中小企業で「社内準備」が多い背景には、以下のような理由と、それに伴う課題があります。
メリット(社内積立が多い理由)
- 自由度が高い: 支給金額の算定方法や、積立方法、時期などを会社の経営状況に合わせて自由に決められる点です。
- 運用益が会社に残る: 積立金を会社の事業資金として活用し、その運用益を会社の収益にできる点です(ただし、積立金を保全していない場合)。
課題とリスク
社内積立には、以下のような大きなリスクも伴います。
- 資金繰りリスク(最も重要):
- 退職金は、長年積み立てて一括で支払う性質上、特に長年勤務した従業員が複数同時に退職した場合、一度に数千万円単位の支払いが発生し、会社の資金繰りを急激に圧迫する可能性があります。
- 損金算入の制限:
- 社内での積立金は、原則として税務上の損金(費用)として認められません。退職金を実際に支払った年に、初めて損金として計上できます。
- 資産の保全性:
- 積立金が会社内部にあるため、万が一、会社が倒産したり経営が悪化したりした場合、従業員への退職金の支払いができなくなるリスクが高いです。
最近の傾向
このような社内積立のリスクを避けるため、中小企業では以下のような「外部積立型」の制度を導入したり、社内積立と併用したりするケースが増えています。
- 中小企業退職金共済制度(中退共)
- 企業型確定拠出年金(企業型DC)
退職金制度を導入する際は、将来の資金繰りリスクと税制優遇、従業員への安全性を総合的に判断し、社外積立型の制度を主軸にすることを検討することをおすすめします。
外部制度方式
退職金制度を自社で運営するのは大変なので、中小企業は外部制度を利用しているところが多いようです。
中小企業退職金共済制度
国の制度であり、独立行政法人 勤労者退職金共済機構(中退共)が運営しています。
退職金の通算: 一定の要件を満たせば、転職した場合などに加入期間を通算できます。
対象企業: 業種によって異なりますが、常用従業員数や資本金の額が一定以下の中小企業が加入できます。
例:一般業種(製造・建設業等)は常用従業員数300人以下、または資本金3億円以下など。
仕組み: 事業主が中退共と共済契約を結び、毎月の掛金を金融機関に納付します。従業員が退職した際は、中退共から直接退職金が支払われます。
主な特色:
国の助成: 新規加入や掛金月額を増額する際などに、国から掛金の一部について助成があります(一定の要件あり)。
税制上の優遇: 掛金は全額、法人企業では損金、個人企業では必要経費として非課税になります。
管理の簡便さ: 掛金は口座振替で、退職金は中退共から直接従業員へ支払われるため、事業主の手間が少ないです。
特定退職金共済
商工会や商工会議所などの特定退職金共済団体が実施する共済制度です。
特徴: 運営元が中退共とは異なります。一般的に国の助成金はありませんが、団体によって独自のサービスや規約があります。
仕組み: 団体が生命保険会社と契約して従業員の退職金を準備する形式が多いです。
企業型確定拠出年金
国が定めた確定拠出年金法による年金制度で、会社が毎月掛金を拠出し、従業員が年金資産を運用します。会社は従業員に対して毎月の掛金額を約束しますが最終的な受給額は約束しません。定年退職を迎える60歳以降に、積み立ててきた年金資産を退職一時金、もしくは年金の形式で受け取り、受取額は運用成果によって変わります。
確定給付企業年金
確定給付企業年金法による年金制度で、規約型と基金型の2種類があります。規約型の設立には300人以上の加入者が必要で、信託銀行や保険会社などに掛金を拠出し、年金資産を管理・運用し、年金を給付します。基金型に人数要件はなく、企業年金基金が年金資産を管理運用します。退職時の一時金としては受け取れず、年金給付になります。
規程を整備する
退職金を支給する会社は、その制度の内容を就業規則に定めなければなりません。
就業規則には「退職金については退職金規程による」などと簡潔に記載して、別途、退職金規程を定めるのが一般的です。制度の組み立てによってどのように規定するかが異なります。