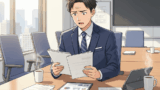労働基準法における時間管理除外規定
一定の業種と業務には労働基準法の労働時間、休憩、休日に関する規定が適用されません。
労働基準法第41条 この章、第6章及び第6章の2で定める労働時間、休憩及び休日に関する規定は、次の各号の一に該当する労働者については適用しない。
一 農業水産業の労働時間
二 事業の種類にかかわらず監督若しくは管理の地位にある者又は機密の事務を取り扱う者
三 監視断続的労働
このページでは、二の「管理監督者等」について解説します。
事業経営をするためには、一定の範囲の労働者には、労働時間や休憩、休日についての規制を超えて活動してもらう必要があるだろうという考えです。この条文にある「監督若しくは管理の地位にある者」を縮めて「管理監督者」と呼んでいます。
労働時間、休憩、休日に関する規定とは
労働時間
労働基準法において、労働者の労働時間の上限は、1日8時間および1週40時間と定められています。また、時間外労働は原則として月45時間、年360時間を上限とします。
管理監督者には労働時間の上限規制が適用されません。時間外労働の上限も対象外なので、残業時間に規制がなく残業手当の支払いもありません。
ただし、深夜労働の割増は管理監督者にも適用されます。
また、過重労働を防止するため、使用者は管理監督者についても労働時間を把握しなければなりません。
休憩
労働基準法は一定の休憩について定めています。これに違反して休憩を与えないことがあれば罰則が適用されます。しかし、管理監督者には休憩についての規定も適用されないので、休憩しないで働いたとしても労働基準法の休憩規定に違反しません。
休日
労働者に対して、毎週少くとも一回の休日、または四週間を通じ四日以上の休日を与えなければならないと決まっています。
この規定は、管理監督者には適用されません。管理監督者には週1回などの法定休日を与えなくても良いのです。
ただし、有給休暇には休日のように管理監督者を除外する規定はありません。管理監督者も有給休暇をとることができます。労働基準法は「休日」と書いています。休日と休暇は別であることに留意が必要です。
管理監督者と管理職は違います
労働基準法にでてくる管理監督者は、会社の課長や部長といった管理職と同じではありません。重なる部分はありますが、違うものだととらえた方が間違いがないでしょう。
「管理職」と「管理監督者」を混同して残業代などを支払わないのであれば、賃金の未払いという労働基準法違反になるおそれがあります。
管理監督者性を否定する重要な要素
通達では、管理監督者性を否定する判断要素を示しています。
職務内容、責任と権限
① アルバイト・パート等の採用について責任と権限がない
② アルバイト・パート等の解雇について職務内容に含まれず、実質的に関与しない
③ 部下の人事考課について職務内容に含まれず、実質的に関与しない
④ 勤務割表の作成、所定時間外労働の命令について責任と権限がない
勤務様態
① 遅刻、早退等により減給の制裁、人事考課での負の評価など不利益な取扱いがされる
補強要素
① 長時間労働を余儀なくされるなど、実際には労働時間に関する裁量がほとんどない
② 労働時間の規制を受ける部下と同様の勤務様態が労働時間の大半を占める
賃金等の待遇
① 時間単価換算した場合にアルバイト・パート等の賃金額に満たない
② 時間単価換算した場合に最低賃金額に満たない
補強要素
① 役職手当などの優遇措置が割増賃金が支払われない事を考慮すると十分でなく労働者の保護に欠ける
② 年間の賃金総額が一般労働者と比べ同程度以下である
通達をふまえた対応
上記で示された要素に一つでも該当すると、管理監督者に該当しない可能性が高いとされています。では、一つも該当しないと大丈夫か? そうでもなさそうです。
通達には、「否定要素をすべてクリアできたからといって必ずしも管理監督者に該当するとはいえない。」「実態判断する」とも書かれています。
つまり、管理監督者として認められるケースは極めて限定的だということです。
厚労省のパンフレットには「労働条件の決定その他労務管理について、経営者と一体的な立場にあり、労働時間等の規制の枠を超えて活動せざるを得ない重要な職務内容を有していなければ、管理監督者とは言えません。」とも記載されています。
つまり以下の3項目です。
① 経営者と一体的な立場である
② 労働時間の規制の枠を超えて活動せざるを得ない
③ 重要な職務内容を有している
上記の3項目に照らして再検討する必要があります。
これにあてはまるのは、工場長や支店長、営業部長などが考えられますが、単に肩書だけでなく、実質的な権限があるかどうかで判断しなければなりません。本社の了解がなければパートの採用もできないようであれば経営者と一体的な立場とは言えませんし、他の従業員と同様に毎日定時の出社が義務付けれらているような働き方では労働時間の規制の枠を超えていると言えません。
なお、「管理監督者」であっても長時間労働をさせて健康を害するようなことがあれば会社は安全配慮義務に違反します。また、管理監督者であっても深夜割増賃金は払わなくてはならないので、労働時間の把握はしなければなりません。
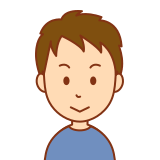
裁判になれば管理監督者と認められるケースはさらに限定的のようです。どうであれば認められるかという線を引くことはできませんが、工場長や支店長という肩書を与えられて他の従業員よりも給料が高くても、他の従業員と同様の現場仕事で忙しくしている場合は、まず管理監督者とは認められないでしょう。