 労働災害
労働災害 脳・心臓疾患の労災補償について
脳・心臓疾患の労災補償に関して新しい通達が出ています。基補発 10 1 8第1号令和5年10月18日「血管病変等を著しく増悪させる業務による脳血管疾患及び虚血性心疾患等の認定基準に係る運用上の留意点について」に基づいて、脳・心臓疾患の労災認...
 労働災害
労働災害  労働災害
労働災害  労働災害
労働災害  労働災害
労働災害 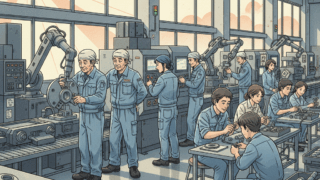 労働災害
労働災害  労働災害
労働災害  労働災害
労働災害 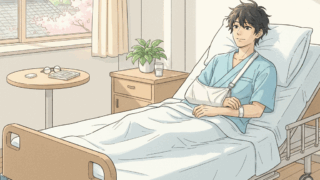 労働災害
労働災害  労働災害
労働災害 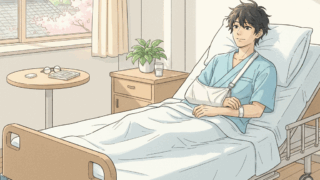 労働災害
労働災害