 採用
採用 労働条件の明示は電子メール等でもよい
労働条件通知書を電子メールなどの電磁的方法で送ることは可能です。2019年4月1日の労働基準法施行規則改正により、書面交付が原則だった労働条件通知が、労働者が希望した場合に限り、電子メールやFAX、SNS(ソーシャル・ネットワーキング・サー...
 採用
採用  採用
採用  採用
採用 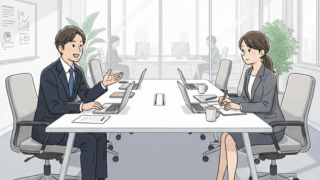 採用
採用  採用
採用  採用
採用  採用
採用  採用
採用  採用
採用 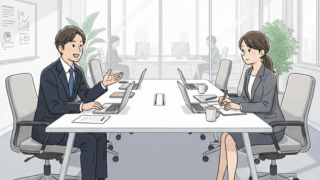 採用
採用