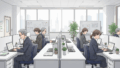「派遣の三年ルール」について解説します。
三年ルールとは?
派遣の三年ルールとは、有期雇用の派遣社員が、同じ事業所・同じ組織単位(部署など)で3年を超えて働けない、という規定労働者派遣法に定められた規定です
このルールには、「事業所単位」と「個人単位」の2つの適用制限があります。
制限の種類と内容
事業所単位の制限
同一事業所において、派遣社員を 3年を超えて受け入れてはいけない という制限です。
ただし、労働組合(または過半数代表者)への「意見聴取」を行うことで、最長3年までの延長が可能です。
労働組合等への意見聴取は、事業所単位の期間制限の抵触日の1ヶ月前までに意見を聴く必要があります。1回の意見聴取で延長できる期間は3年までです。以降も同じ手続きによってさらに延長が可能です。
意見聴取で異議が出された場合、労働者派遣法では、受け入れられなくなるという規定はありませんが、時間をかけた協議が必要になり、実質的には受け入れられなくなると考えられます。
意見聴取をしないで延長した場合、過半数代表者の選出方法が適正でなかった場合など、適正な手続きがおこなわれなかったときは、派遣法違反になるので、労働契約申込みみなし制度の対象になる可能性があります。
また、派遣を一旦休止してから3か月以上あける(クーリング期間)と、それまでの勤務が継続とみなされず、再び3年まで派遣可能とされるケースもあります。
個人単位の制限
同一の派遣労働者を、派遣先の事業所における同一の組織単位に対し派遣できる期間は、3年が限度です。
派遣先が労働組合等との協議を経て事業所単位での3年制限を延長したとしても、同じ人を同じ課で使い続けることはできません。
同一の組織単位に継続して3年間派遣される見込みがある場合、派遣終了後の雇用を継続させるための措置を講じることが、義務付けられています。
この制限には労働組合の意見による延長の制度がないので、完全に「リセット」するには部署異動や3か月以上のクーリングが必要です。
同一の組織単位というのは、「課」が想定されています。よって、ある課への派遣が終了しても、あらためて違う課に派遣されるのであれば、その派遣社員はあと3年同じ会社で働き続けることが可能になります。
3年ルールの例外
以下のような派遣社員は、三年ルールの対象外となります:
- 派遣元と無期雇用契約を結んでいる派遣社員。
- 60歳以上の派遣社員。
- 有期プロジェクト業務に従事しているケース。
- 日数が限定された業務(例:月10日以下の勤務など)。
- 産前産後休業・育児・介護休業の代替業務として従事している場合。
三年ルールへの対応策
三年ルールが適用される場合、以下のような対応策があります。
- 派遣社員を交代する。
- 部署を異動する(例:「経理課」から「営業課」など)とリセットされ、再び3年間派遣が可能(クーリング期間をおく)。
- 派遣元で無期雇用に変更することで、3年ルールの対象外にする。
- 派遣先企業による直接雇用への切り替え(正社員や契約社員など)。
離職後1年以内の労働者
正社員、アルバイト等を問わず、ある会社で直接雇用されていた労働者は、60歳以上の定年退職者を除いて、離職後1年以内はその同じ会社で派遣労働者として働くことが禁止されています。
禁止される派遣先は事業者単位となっているので、例えば、チェーン展開している会社のある店舗を退職した労働者は、1年以内は同じ会社の違う店舗へ派遣されることができません。一方、法人格が違うグループ企業内の別会社であれば、規制の対象外になります。