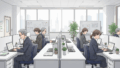定年後の再雇用制度とは
再雇用制度は、継続雇用制度の一つで、定年退職した従業員を、改めて雇用し直す制度です。これは、企業が65歳までの雇用確保義務を果たすための主要な方法の一つです。
制度の概要
再雇用制度では、定年を迎えた従業員との雇用契約を一旦終了させ、退職金を支払います。その後、本人の希望があれば、改めて新しい雇用契約を結びます。
雇用形態: 多くのケースで、正社員から嘱託社員や契約社員などの有期雇用契約に切り替わります。
労働条件: 勤務時間や給与、担当業務が変更されることが一般的です。
企業側のメリットは、経験豊富なベテラン社員の知識やスキルを活かし続けることができます。また、人件費を抑えながら人材を確保できることです。
従業員のメリットは、65歳まで安定して働き続けることができ、経済的な不安を軽減できることです。
この制度は、多くの企業が導入しており、高齢者雇用における最も一般的な選択肢となっています。
再雇用制度は、定年の年齢でいったん退職させ、新たな労働条件による雇用契約を結んで雇用を継続する制度です。社員としての定年は従来通り60歳のままとして、その後は65歳まで年契約の有期雇用を更新する制度です。この場合、希望者を必ず再雇用しなければなりません。
再雇用制度を採用する場合は、関係する規程を作成しなければなりません。
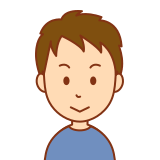
継続雇用制度と再雇用制度の違いが分かりにくいのですが、厚生労働省のホームページ内の「高齢者の雇用」では『「継続雇用制度」とは、雇用している高年齢者を、本人が希望すれば定年後も引き続いて雇用する、「再雇用制度」などの制度をいいます。』と説明しています。つまり、再雇用制度は継続雇用制度の一つということです。
再雇用制度の注意点
再雇用の契約期間
再雇用契約は通常1年契約にして65歳まで更新を続けることにするのが一般的です。途中更新なしの5年契約(65歳に達する月まで)にすることもできます。
待遇の扱い
新しい労働契約を結ぶことになるので、双方合意すれば、法に違反しない範囲であればどのような労働条件にすることも可能です。ただし、実際には、定年前の給与や仕事内容と一定程度の連続性が求められています。
定年前より給与が下がるのが一般的です。定年前と同じ業務量が同じで責任の程度も同じであるのに待遇だけ引き下げることは問題視されています。
有給休暇の扱い
定年退職と再雇用の間に空白期間がないのであれば、年次有給休暇は定年以前の勤続年数を通算した日数が付与されます。
退職金の扱い
定年後再雇用は定年退職をしたうえで、再び雇用される仕組みです。退職金は、退職を支給事由にしているので支払わなければなりません。
就業規則を改定し、定年前に労働契約を変更することができれば、退職金の支払を再雇用契約期間が終了した時点にすることも可能です。
グループ企業での再雇用
再雇用は、自社だけでなくグループ企業での再雇用も雇用確保措置の一つとして認められます。
無期転換の除外
一般の有期雇用労働者は、有期雇用契約を更新して5年になると無期雇用契約への転換請求ができます。都道府県労働局から「第2種計画」の認定を受ければ、5年ルールの対象外にすることができます。有期雇用特別措置法に定められています。
説明会
再雇用制度を就業規則等があり、その内容が周知されている会社でも、定年年齢が近づいた当人は、会社から具体的な説明がないと不安になってしまいます。定年退職予定日の1年前を目安に説明会を実施するとよいでしょう。
退職の手続きをする
定年年齢に達したときに、就業規則の定年退職が適用されるので退職手続きをとります。再雇用されることが決まっている場合は、通常の退職手続きと異なるところがあります。
1.就業規則の定年条項が適用されるので退職届は求めません。
2.失業ではないので離職票は発行しません。
雇用契約書を取り交わす
新たに雇用する形になるので、賃金や労働時間が変わればもちろん、変わらなかったとしても、新たに、会社から労働条件を通知し、雇用契約書を取り交わす必要があります。
再雇用後の手続き
労働者名簿の追記
労働者名簿に、変更事項の追記として、定年退職と再雇用を記載します。再雇用の際に新たに労働者名簿を調整してもかまいません。
社会保険の同日得喪の手続き
定年後再雇用の適用をうけ、それにより賃金が低下した場合には、被保険者資格喪失届および被保険者資格取得届を同時に、定年退職日の翌日付けで提出します。「同日得喪」という手続きです。
賃金が低下した場合、原則的な処理では、差し引かれる社会保険料はすぐには変わりません。通常の手続きでは4ヶ月目から社会保険料が変更になります。この手続きによって、社会保険の月額変更に該当することを待たずに、標準報酬月額を引き下げることができ、社会保険料負担を軽減することができます。
雇用保険の手続き
雇用保険については、特に手続きは必要ありません。
ただし、労働条件の変更によって、所定労働時間が週20時間未満になる場合は、雇用保険の加入条件から外れるため、資格喪失届が必要になります。
高年齢雇用継続給付
再雇用や再就職で賃金が大きく下がったときに、労働者は雇用保険の高年齢雇用継続給付を受給することができます。在籍している労働者に関する手続きなので原則として事業主が手続きを行います。
70歳までの就業確保措置
以上の説明は65歳までの雇用確保措置です。高齢者雇用安定法の2021年4月の改正施行で、70歳までの高年齢者の就業機会を確保する「高年齢者就業確保措置」が追加されています。