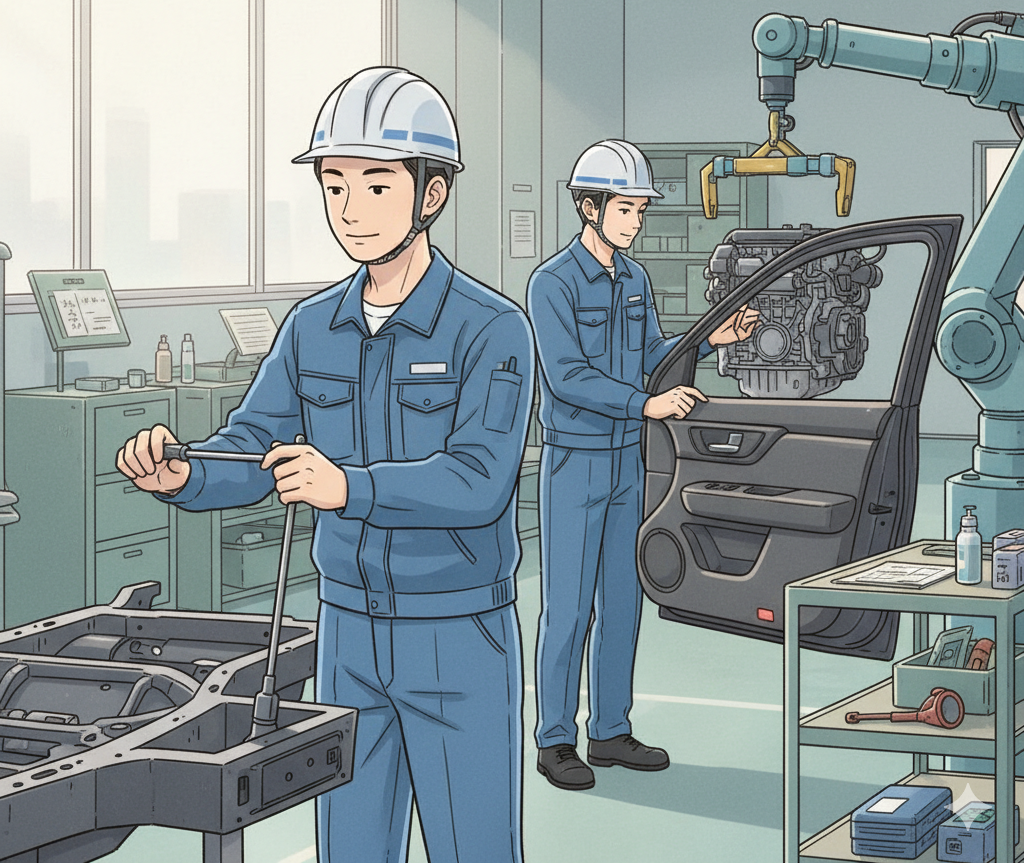労働安全衛生法 第62条「適正な配置」とは?
労働安全衛生法第62条は、以下のように定めています。
事業者は、中高年齢者その他労働災害の防止上その就業に当たつて特に配慮を必要とする者については、これらの者の心身の条件に応じて適正な配置を行なうように努めなければならない。
これは、
「会社は、中高年の人や、その他健康面などで特に気をつけないといけない人(例えば、持病がある人など)に対しては、その人の体の状態や心の状態に合った仕事を割り当てるように努力しなければなりませんよ」
ということです。
年齢を重ねると、身体能力の低下、例えば視力や聴力の低下、筋力の衰え、反応速度の遅れなどが生じることがあります。また、持病があれば、特定の作業で健康状態が悪化したり、事故につながったりするリスクが高まります。
このような状況で無理な配置をしてしまうと、労働災害(怪我や病気)につながる可能性が高まるため、それを防ぐために「努力義務」として定められているものです。
なお、中高年齢者とは何歳からなのかは、労働安全衛生法上では定められていません。高年齢者等の雇用の安定等に関する法律施行規則では45歳以上を中高年齢者と定めており、これに準拠して考えてよいと思われます。
「適正な」とは?
結論から言うと、明確な数値基準や具体的なマニュアルは、法律で定められていません。
なぜなら、
「中高年齢者」の心身の状況は人それぞれ、「特に配慮を必要とする者」の状況も様々、業務の内容も会社によって多種多様なので、具体的に指し示すことが難しいからです。
そのため、この条文は、個別の状況に合わせて会社が「努力する」ことを求めているのです。
しかし、「やるように努力したけれど結果的には何もしていない」のでは努力義務に応えていることにはなりません。厚生労働省は、この「適正な配置」を実現するために、会社が具体的にどのようなことに取り組むべきかを示すガイドラインや指針を出しています。特に、近年増加傾向にある高齢者の労働災害を防ぐため、「高年齢労働者の安全と健康確保のためのガイドライン(通称:エイジフレンドリーガイドライン)」が公表されています。
「エイジフレンドリーガイドライン」などから
会社は以下の視点で具体的な配慮を行うことが求められます。
心身の状況の把握
定期健康診断の結果を適切に活用する。
本人からの健康状態に関する申告(疲れやすい、腰が痛いなど)に耳を傾ける。
必要に応じて、体力チェックなどを実施し、客観的に身体能力を把握する。
作業環境の改善
身体的負担の軽減
重いものを持つ作業を避ける、または台車やリフトなどの補助器具を導入する。
不自然な姿勢での作業をなくすため、作業台の高さ調整や作業内容の変更を行う。
休憩を適切に取る、作業ペースを調整できるようにする。
安全対策の強化
転倒しやすい段差や滑りやすい床を解消する。
照明を明るくする、作業通路を広くする。
危険な機械には安全装置を設置し、操作がシンプルになるよう工夫する。
暑さ・寒さ対策
暑い場所には涼しい休憩所を設ける、空調を調整する。
寒い場所には防寒対策を講じる。
作業内容・業務の調整
能力に見合った業務への配置
例えば、視力が低下した中高年齢者には、細かい作業や危険を伴う運転業務などを避け、より適した業務へ配置転換を検討する。
記憶力や反応速度の低下が見られる場合には、一度に多くの情報を処理する業務や、とっさの判断が求められる業務を避けるなどの配慮。
教育・訓練の工夫
新しい作業や複雑な作業を任せる際には、若年層よりも時間をかけて丁寧に指導する。
図や写真を使ったマニュアルを用意するなど、理解しやすい方法で教育を行う。
勤務形態の柔軟化
夜勤日数を減らす、一人での夜勤を避ける、夜勤後の休日を十分確保するなど、勤務形態を考慮する。
相談体制の整備
労働者が自分の体調や業務に関する不安を気軽に相談できる窓口や担当者を設ける。
まとめ
「適正な配置」に具体的な数値基準はありませんが、それは「会社が個々の労働者の状況をよく見て、一番良い方法を考えてくださいね」というメッセージだととらえましょう。
そして、この措置をとるにあたっては、以下の点を意識しましょう。
一方的に決めるのではなく、本人とよく話し合うこと。
健康診断の結果や日々の業務中の様子をよく観察すること。
「年齢や持病があるから無理」と決めつけず、どうすれば安全に、かつ能力を発揮して働けるかを一緒に考えること。
必要に応じて、作業環境の改善や業務内容の調整を検討し、実行すること。
これらの取り組みを通じて、労働災害を未然に防ぎ、すべての社員が長く健康に安心して働ける職場環境を作っていくことが、労働安全衛生法第62条の目指すところです。