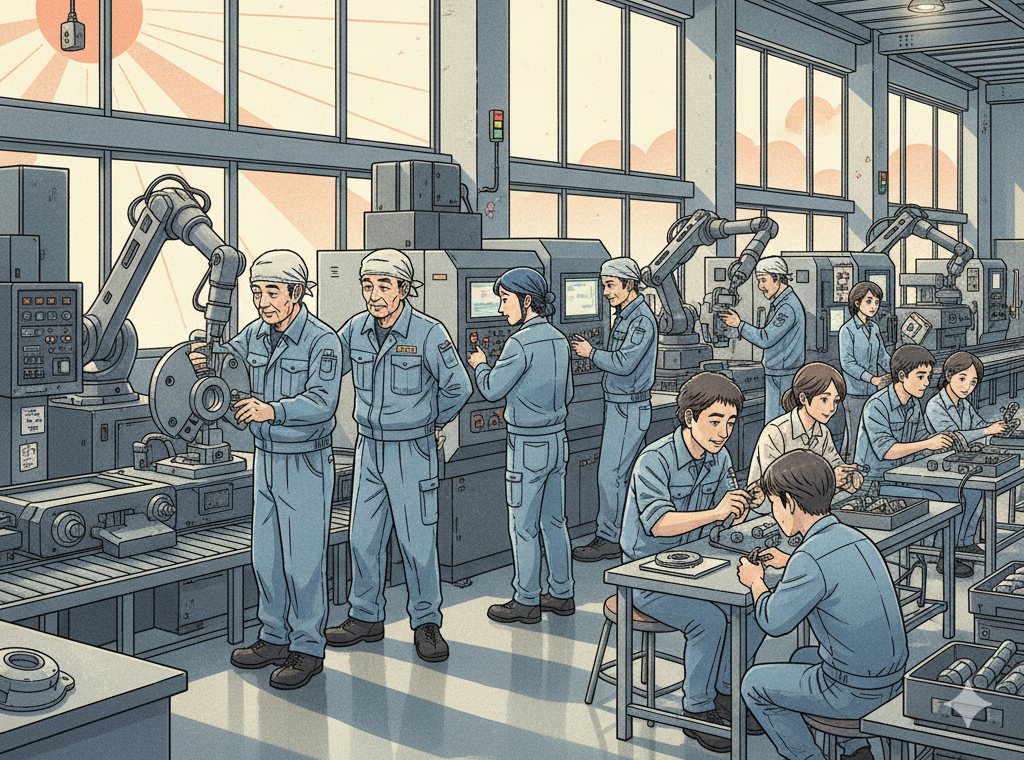労働基準法 第一章:総則(そうそく)
「総則」とは、法律全体の基本的な考え方やルール(目的、用語の定義など)を定める部分のことです。ここをしっかり理解することで、その後の各条文の意味がより深く理解できます。
労働基準法第一章総則は、第一条から第八条まであります。以下、条毎に説明します。
第一条:労働条件の原則
条文
「労働条件は、労働者が人たるに値する生活を営むための必要を充たすべきものでなければならない。この法律で定める労働条件の基準は最低のものであるから、労働関係の当事者は、この基準を理由として労働条件を低下させてはならないことはもとより、その向上を図るように努めなければならない。」
解説
この条文は、労働基準法が何のためにあるのか、その「目的」を宣言している、最も大切な条文です。
人間らしい生活ができるような労働条件でなければならないという意味です。
労働は、単にお金を稼ぐための手段ではなく、人が人間らしく生きるための基盤である、という考え方です。最低限、健康で文化的な生活を送れるような労働条件を保障することが、この法律の根本にあります。
この法律に書いてある労働条件は、最低限のラインです。
労働基準法で決められている「1日8時間労働」「最低賃金」などは、「これだけは守ってくださいね」という最低限の基準です。会社は、これより悪い条件働かせれば労働基準法違反になります。
「最低基準だからといって、それより労働条件を下げてはいけませんし、むしろ、もっと良くするように頑張ってくださいね」という意味もあります。
つまり、「労働基準法で8時間と書いてあるから、ちょうど8時間ぴったり働かせよう」という考え方ではなく、「8時間を超えてはいけないけれど、できればもっと短い時間にできないか」「もっと働きやすい環境にできないか」など、常に労働条件を改善していく努力を会社も労働者も一緒にするべきだ、という方向性を示しています。
ポイント
第一条は、労働基準法は労働者を守るための最低限のルールであり、それ以上の良い労働条件を目指すべきだ、という理念が込められています。
第二条:労働条件の決定
条文
「労働条件は、労働者と使用者が、対等の立場において決定すべきものである。労働者及び使用者は、労働協約、就業規則及び労働契約を遵守し、誠実に各々その義務を履行しなければならない。」
解説
この条文は、労働条件を決めるときの「基本的な姿勢」について定めています。
労働者と会社(使用者)は、同じ立場で労働条件を決めましょうということです。
本来、会社と労働者では力の差があります(会社の方が強い立場になりがちです)。しかし、労働条件を決める話し合いでは、お互いが「対等」な立場で意見を出し合い、納得して決めましょう、という原則を示しています。
一度決めた労働条件は、会社も労働者も、ちゃんと守りましょうとも定めています。
「労働協約(労働組合と会社が結ぶルール)」「就業規則(会社が作る職場のルール)」「労働契約(個々の労働者と会社が結ぶ約束)」など、ルールを決めたらお互いにそれを守り、それぞれの責任をきちんと果たしましょう、ということです。
ポイント
労働条件は、対等な話し合いで決められ、一度決まったらお互いに誠実に守るべきものだ、という関係性を定めています。
第三条:均等待遇(きんとうたいぐう)
条文
「使用者は、労働者の国籍、信条又は社会的身分を理由として、賃金、労働時間その他の労働条件について、差別的取扱をしてはならない。」
解説
この条文は、「差別禁止」についての非常に重要なルールです。
具体的には、
国籍での差別が禁止です。日本人だから、外国人だから、という理由で労働条件等を差別してはいけません。
信条(しんじょう)での差別が禁止です。信条というのは、思想や宗教、政治的な考え方などを指します。
社会的身分での差別が禁止です。社会的身分というのは、出自(生まれ)、家柄、職業(元々どんな仕事をしていたか)、地位(例えば、会社の役員の子どもかどうかなど)といった、本人の努力ではどうにもならない属性のことです。
これらの理由で、給料を低くしたり、労働時間を長くしたり、その他の働き方(仕事の与え方、休憩の与え方、福利厚生の利用など)で不公平な扱いをしてはいけません。
ポイント
国籍、信条、社会的身分といった、本人の努力では変えられない個人的な属性を理由とした差別は、絶対に禁止されています。
なお、この条文に「性別」は含まれていませんが、性別による差別は「男女雇用機会均等法」という別の法律で禁止されています。また、「能力」や「成果」に基づく差は、この条文の差別にはあたりません。
第四条:男女同一賃金の原則
条文
「使用者は、労働者が女性であることを理由として、賃金について、男性と差別的取扱いをしてはならない。」
解説
この条文は、「男女の賃金格差禁止」についてのルールです。
同じ仕事内容で同じ能力を持っているのに、「女性だから」という理由だけで男性よりも賃金が低い、というような差別を禁止しています。
ポイント
性別による賃金差別は明確に禁止されています。
実際の職場では、役職や職務内容、勤続年数などが異なるために賃金に差が出ることがありますが、これは「性別を理由とした差別」にはあたりません。あくまで「女性であること」が賃金差の理由になることが禁止されています。
第5条:強制労働の禁止
条文
「使用者は、暴行、脅迫、監禁その他精神又は身体の自由を不当に拘束する手段によつて、労働者の意思に反して労働を強制してはならない。」
解説
この条文は、「会社は、暴力や脅しなどで、無理やり働かせてはいけません」という、人権に関わる非常に重要なルールです。
社員が「働きたくない」と思っているのに、殴ったり、脅したり、「帰らせないぞ」と閉じ込めたりして、無理やり仕事をさせることは絶対に許されません。違反した場合は、1年以上10年以下の懲役または20万円以上300万円以下の罰金が科せられます。これは、労働基準法で定められた罰則の中で最も重いものです。
ポイント
いかなる理由があっても強制的な労働は禁止されています。
第六条:中間搾取の排除
条文
「何人も、法律に基いて許される場合の外、業として他人の就業に介入して利益を得てはならない。」
解説
この条文は、「ピンハネ」などを禁止するルールです。
誰であっても、法律で認められている場合を除いて、他人が仕事に就くことに関わって、そこからお金を取ってはいけません。
例えば、「仕事を紹介してやる代わりに、紹介料をよこせ」とか、「君の給料は20万円だけど、1割の2万円は俺の取り分だ」といった行為を禁止しています。
「法律で認められている場合」というのは、例えば、職業安定法に基づいて許可を得た「有料職業紹介事業」など、きちんとルールに則って行われる事業のことです。
ポイント
労働者の労働によって得られる利益から、不当に第三者がお金を取ること(中間搾取)を禁止し、労働者が得た対価が正当に本人に支払われることを保障しています。
第七条:公民権行使の保障
条文
「使用者は、労働者が労働時間中に、選挙権その他公民としての権利を行使するために必要な時間を請求した場合においては、拒んではならない。但し、権利の行使を妨げない限りにおいて、時刻の変更をさせることができる。」
解説
この条文は、「社員が社会の一員としての権利を行使するのを邪魔してはいけません」というルールです。
「社員が、選挙に行ったり、裁判員として裁判に参加したりするなど、国民としての権利を行使するために、仕事中ですが出かけてきますと言ったら、会社はそれを拒否してはいけません」
社員が投票に行くために数時間休む、あるいは裁判員制度で裁判に参加するために数日間会社を休む、といった場合も、会社はそれを認めなければなりません。
「ただし、権利の行使の妨げにならない範囲で、時間の変更をお願いすることはできます」
例えば、「どうしても午前中に投票に行きたい」という社員に、「午後にも投票所は開いているから、午後にしてもらえないか」とお願いすることは可能です。
ポイント
労働者が国民としての権利(公民権)を行使する自由を保障しています。
この権利を行使している時間に対して会社が賃金を支払う義務はありません。無給でも問題ありませんが、多くの会社では有給休暇を充てるなどの配慮をしています。
第八条:定義
条文
「この法律で「労働者」とは、職業の種類を問わず、事業又は事務所に使用される者で、賃金を支払われる者をいう。
この法律で「使用者」とは、事業主又は事業の経営担当者その他その事業の労働者に関する事項について、事業主のために行為をするすべての者をいう。
この法律で「賃金」とは、賃金、給料、手当、賞与その他名称の如何を問わず、労働の対償として使用者が労働者に支払うすべてのものをいう。」
解説
この条文は、労働基準法で使われる基本的な言葉の意味(定義)を説明しています。この定義が、この法律が誰に適用されるのか、何を指すのかを明確にします。
労働者(ろうどうしゃ)とは?
「職業の種類を問わず」: 正社員、パート、アルバイト、契約社員など、どんな雇用形態でも関係ありません。
「事業又は事務所に使用される者で」の意味は、会社やお店、事務所などで働いている人、ということです。
「賃金を支払われる者をいう」の意味は、働いたことに対して、給料をもらっている人、ということです。
使用者(しようしゃ)とは?
「事業主又は事業の経営担当者」とは、 会社の社長や役員など、実際に会社を経営している人や、その責任者のことです。
「その他その事業の労働者に関する事項について、事業主のために行為をするすべての者」とは、社長だけでなく、人事部長、工場長、店長、課長など、労働者を指揮監督したり、採用・解雇・賃金に関わる決定権を持っていたりする人も含まれます。つまり、実際に労働者に指示を出したり、労働条件に関わったりする立場の人も「使用者」として労働基準法上の責任を負います。
賃金(ちんぎん)とは?
「賃金、給料、手当、賞与その他名称の如何を問わず」とは、「給料」や「ボーナス」だけでなく、「残業手当」「通勤手当」「役職手当」など、どんな名前がついていても同じという意味です。
「労働の対償として使用者が労働者に支払うすべてのもの」とは、「労働の対価(働いたことに対する見返り)」として会社が労働者に支払うお金のことです。
まとめ
労働基準法第一章は、この法律の魂とも言える部分です。
労働者の人間らしい生活を保障する(第1条)という目的。
対等な立場で労働条件を決め、守る(第2条)という姿勢。
差別や強制労働を許さない(第3条、第4条、第5条)という基本的な人権の尊重。
不当な搾取を排除する(第6条)という公平性。
国民としての権利行使を妨げない(第7条)という自由の保障。
そして、「労働者」「使用者」「賃金」という主要な言葉が何を指すのかを明確にする(第8条)ことで、法律が適用される範囲を定めています。
この第一章を理解することで、労働基準法のその他の条文がなぜ存在するのか、どのような考えに基づいているのかが、より深く把握できるはずです。