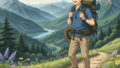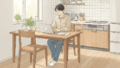計画的付与とは
計画的付与というのは、有給休暇をとる日を計画的に決めることです。
年次有給休暇の計画的付与制度とは、従業員の年次有給休暇の取得率を向上させることを目的とした制度です。
本来、年次有給休暇は労働者が自由に取得時季を指定できるものですが、この制度では、労使協定を締結することを前提に、年次有給休暇のうち5日を超える部分について、会社が計画的に休暇取得日を割り振ることができます(労働基準法第39条第6項)。
制度のポイント
労使協定が必須
導入するには、労働者の過半数で組織する労働組合(ない場合は労働者の過半数を代表する者)との間で、書面による労使協定を締結する必要があります。この労使協定には、計画付与の対象者や日数、具体的な方法などを定めます。
対象となる日数
労働者には、病気や急な用事などの個人的な理由で休暇を取得できるよう、年次有給休暇のうち5日分は自由に取得できる日として残しておかなければなりません。そのため、計画的付与の対象となるのは、付与された有給休暇のうち「5日を超える部分」です。
例:年10日の有給休暇が付与された場合、5日分は労働者が自由に取得でき、残りの5日分を計画的付与の対象とすることができます。
導入の方式
計画的付与には、主に以下の3つの方式があります。
一斉付与方式: 事業場全体または部署全体で、特定の日に一斉に有給休暇を取得させる方式。お盆休みや年末年始の長期休暇と組み合わせて、大型連休とするケースが多く見られます。
グループ別交替制付与方式: 部署や班ごとに交替で休暇を取得させる方式。流通・サービス業など、事業場全体を休みにできない場合に適しています。
個人別計画付与方式: 従業員一人ひとりの希望を聞き、年間の有給休暇取得計画表を作成して取得させる方式。
時季変更権の制限
計画的付与として取得日が決まった有給休暇について、労働者は原則としてその時季を変更することはできません。
導入のメリットと注意点
メリット
従業員が気兼ねなく有給休暇を取得できる。
年間5日の有給休暇取得義務を確実に達成できる。
会社は休暇日を事前に把握できるため、業務計画を立てやすくなる。
注意点
労使協定の締結が必要である。
有給休暇の日数が少ない従業員(入社1年未満の新規採用者など)への対応(特別休暇の付与など)を事前に決めておく必要がある。
一度定めた計画的付与日は、原則として変更できない。
この制度は、有給休暇の取得率が低い企業の改善策として、特に有効な手段の一つとされています。
導入に必要な手続き
就業規則に定める
(有給休暇の計画的付与)
第〇条 5日を超えて付与した年次有給休暇については、従業員の過半数を代表する者との間に協定を締結したときは、その労使協定に定める時季に計画的に取得させることとする。
労使協定を締結する
労働組合または労働者の過半数を代表する者との間で、書面による協定を締結します。この労使協定は労働基準監督署に届け出る必要はありません。
労使協定で定める項目
① 計画的付与の対象者
② 対象となる年次有給休暇の日数
③ 計画的付与の具体的な方法
④ 対象となる年次有給休暇を持たない者の扱い
⑤ 計画的付与日の変更方法
④の対象となる年次有給休暇を持たない者の扱いは、事業所そのものが休みになる制度を採用したときに特に問題になります。休業中の工場にあえて出社させるのも現実的でありません。かと言って、追加の有給休暇を与えたり、休業補償を支払ったりすることも、社員とのバランスを考えると単純な話ではありません。労使でよく話し合い、納得が得られた方法で労使協定を締結する必要があります。
労使協定のサンプル
休暇日指定をしない場合のサンプル
一斉取得をする場合のサンプル
法律
年次有給休暇の計画的付与について定めているのは、労働基準法です。具体的には、労働基準法第39条第6項に規定されています。
一方、労働時間等設定改善法は、企業の働き方改善を包括的に支援する法律です。この法律の中で、年次有給休暇の取得促進が重要な取り組みの一つとして挙げられており、その具体的な手段として計画的付与制度の導入が推奨されています。
要するに、計画的付与制度の法的根拠は労働基準法にあり、その導入を奨励・支援しているのが労働時間等設定改善法という関係性です。