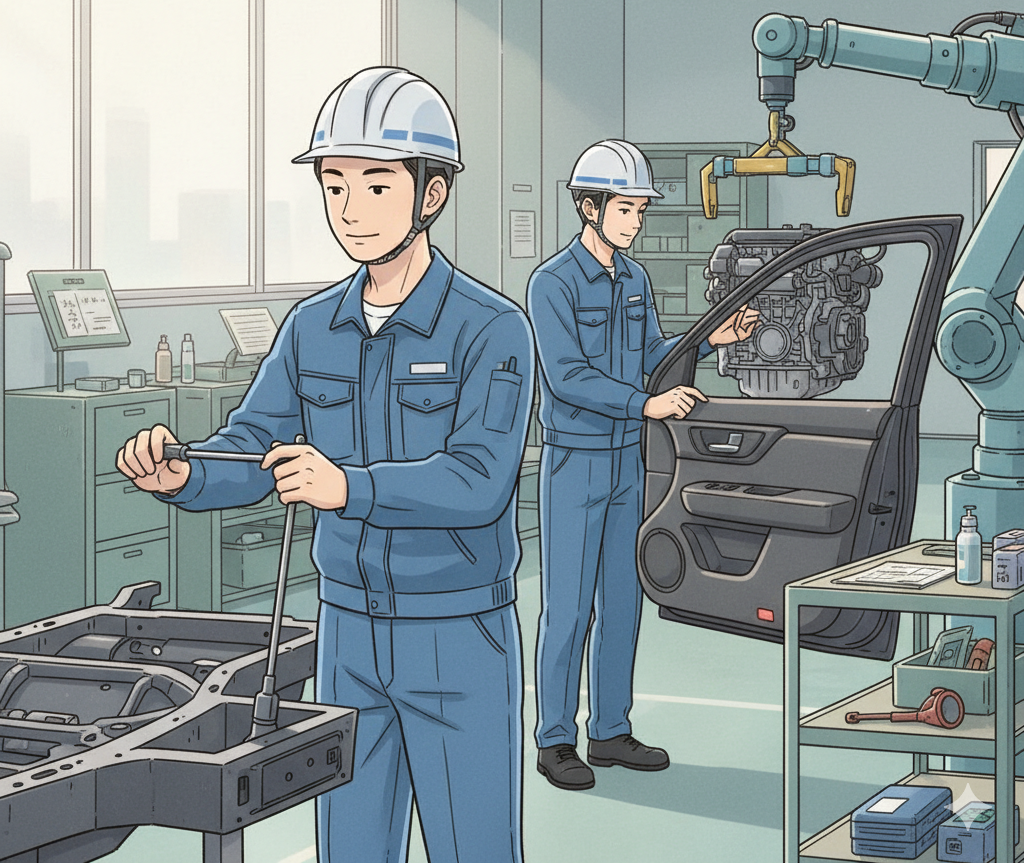徒弟制の弊害排除
労働基準法第69条は、丁稚奉公のような、業務を習得するまでの一定期間、住み込みで家事手伝いを強要されるような慣行から技能取得労働者を保護するために設けられた規定です。
労働基準法第69条 使用者は、徒弟、見習、養成工その他名称の如何を問わず、技能の習得を目的とする者であることを理由として、労働者を酷使してはならない。
労働基準法第69条2 使用者は、技能の習得を目的とする労働者を家事その他技能の習得に関係のない作業に従事させてはならない。
この条文は、徒弟など、つまり「見習いや訓練生を雇う場合」に適用される特別な規定です。通常の従業員とは少し違う扱いになるので、そのポイントをわかりやすく解説します。
通常の労働者と何が違うの?
まず、通常の従業員と、この法律が対象とする「見習いや訓練生」は、何が違うのでしょうか?
- 通常の労働者:労働力を提供し、その対価として給料をもらうことが主な目的です。
- 見習いや訓練生:特定の技能や技術を身につけることが主な目的で、そのための時間や労力が多くを占めます。
例えば、
- 通常の労働者:パン屋さんで雇ったスタッフが、パンを焼いて販売する。
- 見習いや訓練生:将来の職人を目指して、パン作りの技術を教えてもらうために雇われます。
つまり、労働基準法69条は、従業員が「働くこと」よりも「学ぶこと」に重心を置いている場合に適用される可能性があります。
なぜ、特別なルールが必要なの?
なぜ、わざわざこのような規定があるのでしょうか?
それは、技術や技能を次の世代に伝えるためです。
例えば、伝統的な職人の技を教える場合、通常の労働時間や休日のルールを厳格に適用するのが難しいことがあります。指導者が指導できる時間が限られていたり、特定の工程を習得するために時間がかかったりするからです。
そこで、労働基準法69条は、労働基準監督署長の許可があれば、労働時間や休憩、休日に関するルールを柔軟に運用することを認めています。これは、企業が若手を育成し、技術を継承していくことをサポートするための規定なのです。
雇い入れる側が注意すべきこと
「じゃあ、うちの見習いも69条を適用できるの?」と考える方もいるかもしれません。でも、少し待ってください。この規定は、非常に限定的な状況にのみ適用されます。
- 安易な適用はNG!:単に「見習い」と名付けるだけでは適用できません。その実態が、本当に技能習得を主たる目的としているか、客観的に証明できる必要があります。
- 労働基準監督署長の許可が必須:許可なく適用すると、労働基準法違反となります。許可を得るには、技能習得のカリキュラムや労働条件など、詳細な計画を提出し、審査を受ける必要があります。
- 労働者の保護が大前提:この規定は、あくまで「技術継承」と「労働者保護」の両立を目指したものです。見習いだからといって、長時間労働や不当な労働を強制することは決して許されません。
- 労働基準法の適用:労働基準監督署長の許可を得た場合でも、労働時間に関する全ての規定が適用除外されるわけではありません。具体的には、労働時間・休憩・休日に関する規定について特例が認められますが、年次有給休暇や深夜業に関する規定は適用されます。
職業訓練に関する特例
「労働基準法70条」は、特に「認定職業訓練」を行う事業主に関わる特別な規定です。
これは、通常の従業員とは少し異なる、特別な事情がある労働者(訓練生)を雇う場合に適用されます。
労働基準法70条のポイント
労働基準法70条は、特定の職業訓練を受ける労働者について、以下の2つの点に関する特例を定めています。
- 契約期間の特例: 通常、労働契約の期間は原則として3年(専門的知識等を持つ一部の労働者を除き、最長5年)までと定められています。しかし、認定職業訓練を受ける労働者の場合は、訓練に必要な期間で労働契約を結ぶことが認められます。
- 年少者や妊産婦の就業制限の特例: 通常、年少者や妊産婦は、危険な業務や有害な業務、坑内労働などに就くことが法律で制限されています。しかし、認定職業訓練を受ける場合は、都道府県労働局長の許可があれば、訓練に必要な範囲で、これらの業務に就かせることができる場合があります。
なぜ、このような特例があるの?
この規定があるのは、優れた技術や技能を次の世代に確実に伝えるためです。
例えば、特定の職人の技を身につけるためには、危険を伴う作業や、特殊な環境での実習が不可欠な場合があります。しかし、通常の法律を厳格に適用すると、そうした訓練を行うことができません。
そこで、労働基準法70条は、労働者の安全を守ることを前提に、都道府県労働局長の許可を得ることで、訓練に必要な範囲でのみ特例を認めているのです。
個人事業主が注意すべきこと
「じゃあ、うちでもできるかな?」と思った個人事業主の方へ。この規定を適用するには、いくつかの重要な条件があります。
- 「認定職業訓練」であること: 単なる見習いや社内研修ではダメです。この規定が適用されるのは、「職業能力開発促進法」に基づき、都道府県知事などから認定を受けた職業訓練に限られます。
- 労働基準監督署長の許可: 許可がなければ、この特例は適用できません。許可を得るためには、訓練の内容や安全対策などについて厳格な審査を受ける必要があります。
- 最低賃金法は適用される: この規定はあくまで労働時間や就業制限に関するもので、最低賃金法は適用されます。訓練生であっても、最低賃金以上の賃金を支払う必要があります。
- 年次有給休暇も適用される: 労働時間や休日に関する特例があっても、年次有給休暇は通常通りに付与する必要があります。職業訓練を受けている20歳未満の未成年者に、一般労働者よりも多い、12労働日以上が付与される特例があります。