 社会保険
社会保険 人事担当者が知っておくべき「初診日」の知識
障害年金の初診日とは障害年金を受給するには、原則として、初診日の前日において、一定の保険料納付要件を満たしている必要があります。この要件を満たしていない場合、たとえ障害の程度が重くても、年金を受け取ることはできません。したがって、申請時には...
 社会保険
社会保険 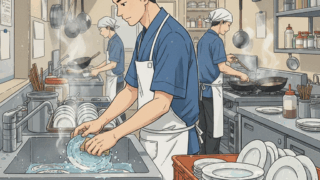 社会保険
社会保険  社会保険
社会保険  社会保険
社会保険 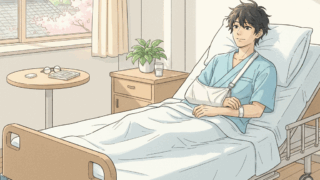 社会保険
社会保険  社会保険
社会保険  社会保険
社会保険  社会保険
社会保険  社会保険
社会保険  社会保険
社会保険