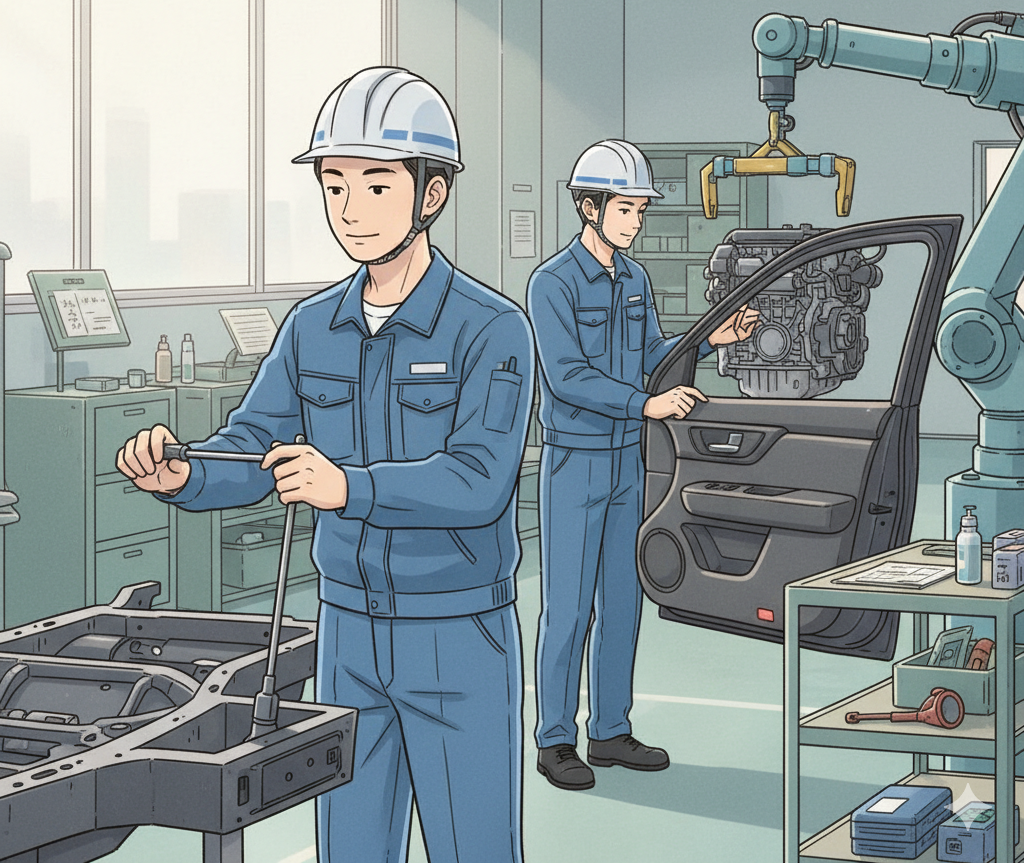作業環境測定とは?
作業環境測定とは、簡単に言うと「職場の空気が、そこで働く人の健康に悪影響を与えないか」を調べることです。具体的には、空気中の有害物質の濃度や、騒音、暑さ・寒さ、放射線などが、法律で定められた基準値を超えていないか、専門家が測って評価します。
この測定の目的は、労働者の健康障害を未然に防ぎ、快適で安全な職場環境を保つことです。
どういう職場がやらなければならないの?
「労働安全衛生法」という法律で、特定の作業場での作業環境測定が義務付けられています。工場だけでなく、事務所などでも対象となる場合があります。
労働安全衛生法第65条 事業者は、有害な業務を行う屋内作業場その他の作業場で、政令で定めるものについて、厚生労働省令で定めるところにより、必要な作業環境測定を行い、及びその結果を記録しておかなければならない。
この規定により、作業環境測定を実施しなければならない作業場は、労働安全衛生法施行令第21条で具体的な作業場が指定されています。
粉じんが発生する作業場: 石や岩、金属などを削ったり加工したりする際に、細かい粉じんが舞う場所(例:鋳物工場、研磨作業場)。
有機溶剤を使用する作業場:塗料や接着剤、シンナーなど、有機溶剤を製造したり使用したりする場所(例:塗装工場、印刷工場)。
特定化学物質を取り扱う作業場:法律で定められた有害な化学物質(例:特定化学物質、鉛)を取り扱う場所。
著しい騒音が発生する作業場:大型の機械や設備が稼働し、常に大きな音が出ている場所(例:プレス工場、製材所)。
暑熱・寒冷・多湿の屋内作業場:極端に暑い、寒い、または湿度が高い屋内作業場。
放射線業務を行う作業場:放射線を取り扱う場所。
酸素欠乏危険場所:酸素濃度が低い、または硫化水素などが発生する可能性のある場所(例:下水処理施設、トンネル工事現場)。
中央管理方式の空気調和設備を設けている事務所:ビルなどで一括して空調管理されている事務所の室内空気環境も測定対象になります。
比較的危険や汚染のおそれが少ない事務所でも、作業環境測定が必要な場合があります。
測定頻度はどうなの?
これらの作業場では、定期的に測定を行うことが義務付けられています。多くの指定作業場では6か月以内ごとに1回ですが、2か月以内ごとに1回、1か月以内ごとに1回、半月以内ごとに1回の作業場もあり、酸素欠乏危険場所のように毎回作業開始前という作業場もあります。
測定結果が第一管理区分(良好な状態)と評価され、かつその状態が継続していると認められる場合は、測定頻度が緩和されることがあります。逆に、第二管理区分や第三管理区分と評価された場合は、改善措置を講じ、より頻繁に測定を行う必要があることもあります。
「〇ヶ月以内ごとに1回」という表現は、その期間を超えない範囲で、という意味です。例えば「6か月以内ごとに1回」であれば、5か月後でも問題ありませんが、7か月後では違反となります。
誰が実施するの?
作業環境測定は、誰でもできるわけではありません。専門的な知識と技術が必要なため、原則として以下のいずれかによって実施されます。
作業環境測定士(有資格者): 厚生労働大臣の登録を受けた「作業環境測定士」という国家資格を持った人が行います。特に法律で「指定作業場」と定められている場所(有機溶剤、特定化学物質、粉じんなど)の測定は、作業環境測定士が行う必要があります。
第一種作業環境測定士: デザイン、サンプリング、分析の全ての業務を行うことができます。
第二種作業環境測定士: サンプリング(試料採取)と分析の一部を行うことができますが、デザインは行えません。
作業環境測定機関: 厚生労働大臣または都道府県労働局長の登録を受けた専門の機関です。多くの企業は、自社に作業環境測定士がいない場合、これらの機関に測定を委託します。
ただし、一部の簡易な測定(酸素濃度など)は、専門の作業主任者(例:酸素欠乏危険作業主任者)が行うことができる場合もあります。
作業環境測定士になるには、年に1回実施される国家試験に合格する必要があります。国家試験に合格しただけでは「作業環境測定士」を名乗ることはできません。合格後、厚生労働大臣が指定する登録講習(通常は1週間程度の講習)を修了し、厚生労働大臣への登録を行うことで、初めて作業環境測定士として業務を行うことができます。
どういう手順で行われるの?
作業環境測定は、主に以下の手順で行われます。
打ち合わせ・デザイン(測定計画の立案)
まず、測定を行う作業場の広さ、作業内容、作業者の行動範囲、使用している有害物質の種類などを詳しく確認します。
この情報をもとに、どこを「単位作業場所」(測定の対象となる作業エリア)とするか、どこで測定するか(測定点)、どのような方法で測定するかといった計画を立てます。これを「デザイン」と呼びます。
通常、複数の測定点(A測定点)を均等に配置し、さらに作業者の暴露が最も大きくなる可能性のある場所(B測定点)を設定します。
サンプリング(試料の採取)
デザインで設定した測定点に、専用の測定機器(ポンプと捕集管など)を設置し、作業場の空気を吸引して有害物質を捕集します。
測定する高さは、人の呼吸域(座っている場合や立っている場合)を考慮し、床から50cm~150cmの範囲で行われます。
測定点ごとに10分~20分かけて空気を採取します。
分析
採取した試料は、作業環境測定機関の分析室に持ち帰り、ガスクロマトグラフや質量分析計などの専門的な分析機器を使って、含まれる有害物質の濃度を正確に分析します。
簡易測定の場合は、その場で検知管などを用いて濃度を判定することもあります。
評価
分析結果に基づき、法律で定められた「管理濃度」と比較して、作業環境の状態を評価します。評価は、以下の3つの管理区分に分類されます。
第一管理区分: 非常に良好な状態。現在の管理を継続します。
第二管理区分: 改善の努力が必要な状態。設備や作業方法の点検を行い、改善に努めます。
第三管理区分: 非常に悪い状態。早急な改善が必要です。設備改善だけでなく、労働者に適切な保護具(マスクなど)を使用させたり、産業医による健康診断の実施なども検討されます。
報告書の作成・提出
測定結果と評価をまとめた報告書が作成され、事業者に提出されます。
事業者はこの報告書を一定期間保存し、必要に応じて労働基準監督署などに提出する義務があります。
測定結果の記録は、対象物質や測定項目によって、3年、5年、7年、40年など、法律で定められた期間保存する義務があります。特に石綿や発がん性物質(特定化学物質の一部)などは、長期にわたる保存が義務付けられています。
まとめ
作業環境測定は、労働者の健康を守るための重要な取り組みです。工場に限らず、有害な因子が発生する可能性のある様々な職場で義務付けられています。専門知識を持った作業環境測定士や作業環境測定機関が、法律に基づいた手順で測定を行い、職場の安全性を評価します。