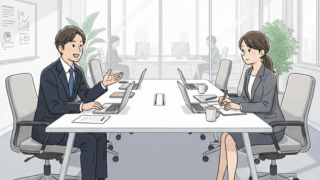 労働契約
労働契約 労働条件通知書を交付すれば雇用契約書はいらないの?
原則は両方必要労働条件通知書はあくまでも使用者が労働者に労働条件を示したものであって、雇用されることについて合意したことを示すものではありません。雇用されることについて合意した文書が雇用契約書です。「労働条件通知書」と「雇用契約書」は、記載...
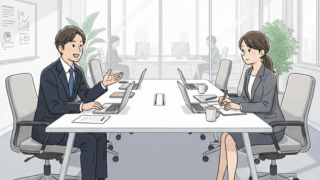 労働契約
労働契約  労働契約
労働契約  労働契約
労働契約  労働契約
労働契約  労働契約
労働契約  労働契約
労働契約  労働契約
労働契約  労働契約
労働契約  労働基準法
労働基準法  労働契約
労働契約