 労働契約
労働契約 労働契約法のあらまし
労働契約法とは労働契約法は、労働契約に関する基本ルールを定め、労働者と使用者の対等な立場での合意と信頼関係に基づく労使関係の形成を目的とした法律です。2008年に施行され、従来の労働基準法や裁判例(判例)で認められていたルールを明文化・体系...
 労働契約
労働契約  労働契約
労働契約 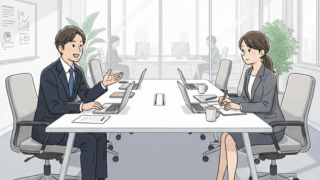 労働契約
労働契約  労働契約
労働契約  労働契約
労働契約  労働契約
労働契約  労働契約
労働契約  労働契約
労働契約  労働契約
労働契約 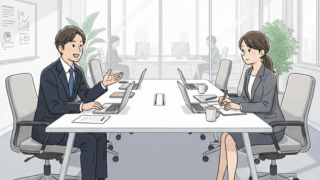 労働契約
労働契約