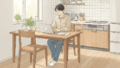年次有給休暇は時間単位で取得できる
新人人事(以下、新): 課長、おはようございます! 年次有給休暇について調べていたのですが、「時間単位年休」という言葉を見つけまして…。普通の有給休暇とどう違うのか、よく分からなくて困っています。教えていただけますでしょうか?
課長: それじゃ説明しよう。時間単位年休は、労働基準法で認められている、比較的新しい有給休暇の取り方なんだ。
時間単位年休の基本的な考え方
課長: まず、通常の年次有給休暇は、1日単位で取得するのが原則だよね。でも、時間単位年休は、その名の通り、有給休暇を1時間単位で取得できるようにする制度なんだ。
新: 1時間単位ですか!それは便利そうですね。ちょっと病院に行きたい時とか、子どものお迎えに少しだけ早く帰りたい時とかに良さそうです。
課長: まさにその通り!労働者のワークライフバランスを向上させる目的で、2009年の労働基準法改正で導入されたんだ。
時間単位年休を導入するための条件
課長: ただ、この時間単位年休は、会社が「必ず導入しなければならない」という義務があるわけではないんだ。導入するには、いくつか条件がある。
労使協定の締結が必要:会社が時間単位年休を導入するには、労働組合(ない場合は労働者の過半数を代表する者)と会社の間で「労使協定」を締結し、管轄の労働基準監督署に届け出る必要があるんだ。
就業規則への明記:労使協定で定めた内容を、就業規則にも明記する必要があるよ。
新: 勝手に始めていいわけではないんですね。ちゃんとルール作りが必要なんですね。
労使協定で定めるべき内容
課長: そうだね。そして、その労使協定では、主に次のことを定める必要があるんだ。
時間単位年休の対象となる労働者の範囲:全従業員にするのか、一部の従業員にするのか、など。
時間単位年休の具体的な取得単位:何時間単位で取得できるのか(1時間単位が一般的)。
1年間の時間単位年休の取得上限時間数:これが重要なポイントで、1年間で取得できる時間単位年休は、5日分までと決まっているんだ。例えば、所定労働時間が8時間の会社なら、8時間 × 5日 = 40時間まで、ということになる。
時間単位年休の申請方法:いつまでに、誰に申請するのか、など。
新: 5日分まで、という上限があるんですね。
労働者が気をつけるべき点
課長: 労働者の視点から見ると、時間単位年休を利用する上で、いくつか気をつけるべき点があるよ。
会社に制度があるか確認する:まず、自分の会社に時間単位年休の制度があるかどうかを確認することが重要だ。なければ利用できないからね。就業規則を確認するか、人事部に問い合わせるのが一番確実だ。
年5日の上限があることを理解する:1年間で5日分(例えば40時間)しか使えないので、計画的に利用することが大切だ。頻繁に利用しすぎると、本当に必要な時に使えなくなってしまう可能性があるからね。
時間単位年休は繰り越しの際に「日」に戻る:これは少し複雑なんだけど、もし今年、時間単位年休を使いきれずに翌年に繰り越す場合、時間単位で残った有給は、「日」単位に換算されて繰り越されるんだ。例えば、今年8時間分の時間単位年休が残っていても、翌年に繰り越されるのは1日分の有給休暇としてカウントされる、ということだ。端数が出てしまう場合は、切り捨てられてしまう可能性もあるから、できるだけ使い切るか、計画的に残しておく必要がある。
労働者の判断に委ねられる:時間単位年休の取得は、労働者の自由な意思に委ねられている。会社は、事業の正常な運営を妨げる場合に限り、時季変更権を行使できるとされているけど、これは日単位の有給休暇と同じだね。ただし、会社が日単位での請求を時間単位に変えることや、時間単位での請求を日単位に変えることはできないんだ。
不利益な扱いは禁止:時間単位年休を取得したことによって、賃金の減額や人事評価での不利益な取り扱いをすることは、法律で禁止されている。
新: 5日分の上限や、繰り越しの際に日単位に戻る、という点は特に注意が必要ですね!これは申請する側も知っておかないと損をしてしまう可能性がありますね。
課長: その通りだ。だからこそ、人事担当として、制度を正しく理解して、従業員にも適切に情報提供することが大事なんだよ。制度があっても、知らなければ利用できないし、誤解があるとかえってトラブルになる可能性もあるからね。
新: はい、よく分かりました! ありがとうございます。
関連情報
労使協定についての補足
労使協定では次の4項目を定めます。
第1:時間単位年休の対象者の範囲を決めます。必ずしも全ての労働者にする必要はありません。
ただし、正常な事業運営の必要性などで対象外の労働者を設定することができますが、例えば、育児を行なう労働者に限るなど取得目的による制限は認められません。
第2:時間単位年休の日数を5日以内で決めます。
第3:時間単位年休一日の時間数を決めます。一日の所定労働時間が8時間であれば、時間で取得した時間数の累計が8時間分になったときに、一日の有給休暇を取得したと数えます。7時間であれば7時間分になったときです。もし、所定労働時間が7時間30分のように端数があれば、(有給休暇に分単位の概念がないため)繰り上げて8時間付与することになります。端数処理を労働者に有利にということです。
第4:一時間以外の時間を単位とする場合はその時間数を決めます。普通は1時間単位で決めると思いますが、選択肢としては2時間、3時間という単位も認められています。
繰り越しについての補足
通達では「当該年度に取得されなかった年次有給休暇の残日数・時間数は、次年度に繰り越されることになるが、 当該次年度の時間単位年休の日数は、 前年度からの繰越分も含めて5日の範囲内となるものであること」と示しています。
時間単位年休は繰り越しされません。例えば、5日分40時間の時間単位年休のうち20時間を使って20時間を残した場合、翌年の時間単位年休は40時間プラス20時間にはならず、あくまでも5日分40時間となります。
年次有給休暇全体としては繰り越されるので、消えるわけではありません。
労使協定と就業規則のサンプル
追加質問(年5日取得義務との関連)
新: 課長、先日教えていただいた時間単位年休について、もう一つ確認したいことがあります。この時間単位年休って、「年5日の有給取得義務化」の対象になるんでしょうか? もし時間単位で5日分取ったら、義務を果たしたことになるんですか?
課長: いい質問だね。そこは、よく誤解されやすいポイントなんだ。結論から言うと、時間単位年休は、「年5日の有給取得義務化」の対象にはならないんだよ。
新: え、そうなんですか!? 時間単位で5日分取得しても、義務は果たせない、ということですか?
課長: そうなんだ。それぞれの制度の目的と、法律上の位置づけが違うからなんだよ。
課長: まず、「年5日の有給取得義務化」というのは、2019年に法律で義務付けられたもので、年に10日以上の有給が付与される従業員に対して、会社は最低5日は有給を取らせないといけない、というルールだよね。これは、従業員にまとまった休みを取ってもらって、心身のリフレッシュを図ることが一番の目的とされているんだ。
新: はい、それは理解しています。
課長: そして、この「年5日」にカウントされるのは、原則として「日単位」で取得された有給休暇なんだ。
課長: 一方、時間単位年休は、従業員がもっと柔軟に有給を使えるように、という目的で作られた制度だ。例えば、病院にちょっと行ったり、子どもの学校行事で少しだけ早く帰ったり、といった短い時間の用事に対応するためにある。会社が労使協定を結んで導入すれば、1年間に最大5日分までを時間で取得できる、という制度だね。
新: 確かに、目的が違いますね。
課長: そうなんだ。だから、この二つの制度は目的も性質も異なるから、時間単位年休を5日分取得したとしても、「年5日の取得義務」を果たしたことにはならないんだ。
簡単に言うと、
年5日義務化: 「年間で最低5日間は、まとまった休みを取りましょうね」という話。
時間単位年休: 「日単位で取るほどじゃないけど、ちょっとだけ時間を休みたい時に便利だよ」という話。
だから、例えば、君が今年、日単位で3日の有給を取って、さらに時間単位年休を20時間(8時間労働の会社なら2.5日分に相当)使ったとするよね。この場合、日単位で取ったのは3日だから、会社としては、残りの2日を日単位で取得させる義務がまだ残っている、ということになるんだ。
新: なるほど!よく分かりました!