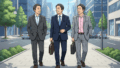会社が設置しなければならない相談窓口の種類
法律で設置が義務付けられている「相談窓口」には次のようなものがあります。
・ハラスメント(セクハラ・パワハラ・マタハラ)に関する相談窓口
・育児・介護休業等に関する相談窓口
・ストレスチェック後の相談窓口(努力義務を含む)
・障がい者からの合理的配慮に関する相談窓口
・公益通報に関する相談窓口
それぞれ役割や守備範囲が異なるため、原則として、それぞれの法令に基づいて個別に設置しなければなりませんが、窓口の一本化や担当者の兼務が禁止されているわけではありません。
相談窓口を一つにまとめればどうなの?
これらの「窓口」を個々に設置するのではなく、「総合窓口」のように1か所にまとめることは、以下のメリットとデメリットを考慮し、適切に運用されれば有効な手段となります。
メリット
どこに相談すればよいか迷うことなく、1か所にアクセスすれば良いので、従業員にとって相談のハードルが下がります。
情報の一元管理: 各種相談内容を一元的に管理することで、企業全体のハラスメントや働き方に関する課題を総合的に把握しやすくなります。
各種問題が複雑に絡み合う場合(例:ハラスメントとメンタルヘルス問題など)でも、担当者間の連携がスムーズに行われ、より包括的な解決に繋がりやすくなります。
窓口の設置や運営に関わるリソース(人員、設備など)を効率的に配分できます。
デメリット・注意点
育児・介護、ハラスメント、メンタルヘルス、障害者対応など、それぞれ専門的な知識や対応が求められます。総合窓口の担当者は、幅広い知識を持ち、必要に応じて専門部署や外部機関と連携できる体制が必要です。
相談内容によっては非常にデリケートな情報が含まれるため、相談者のプライバシー保護や秘密保持が徹底される体制を確立することが不可欠です。相談窓口をまとめた場合、1か所で複数の事案を扱うため、情報管理には特に注意が必要です。
ハラスメントなど、時には会社にとって不都合な情報も寄せられる可能性があります。総合窓口が中立的な立場で対応できる体制を構築することが重要です。外部の専門家(弁護士、社会保険労務士など)との連携も有効です。
総合窓口として機能させる場合でも、それぞれの義務付けられた相談内容について、どこに、どのように相談できるのかを従業員に明確に周知する必要があります。
結論として
「総合窓口」として一元化することは、従業員の利便性向上や情報の一元管理といった点で有効な手段ですが、各相談内容に対する専門性と適切な対応を担保するための体制(担当者の専門知識、研修、外部連携、プライバシー保護の徹底など)をしっかりと構築することが重要です。形式的な設置に留まらず、実質的に機能する窓口として運用されることが、企業にとっての法的リスク低減と健全な職場環境の維持に繋がります。