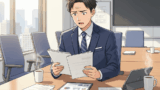個別労働紛争とは
個別労働紛争とは、個々の労働者と事業主(会社)との間に生じた労働条件やその他の労働関係に関する紛争(トラブル)のことを指します。
これは、労働組合と事業主との間で生じる集団的な紛争(労働争議)とは区別されます。近年、労働者の権利意識の高まりや雇用形態の多様化に伴い、この種の紛争が増加傾向にあります。
個別労働紛争の典型的な例
個別労働紛争は多岐にわたりますが、特に多く見られる典型的な事例には以下のようなものがあります。
解雇・雇止めに関する紛争
会社が一方的に労働者を辞めさせる、または有期雇用の契約更新を拒否する際に発生する紛争です。
- 解雇の無効性: 会社から突然「明日から来なくていい」と解雇されたが、その理由に正当性がないとして解雇の撤回や賃金の支払いを求めるケース。
- 雇止め: 契約社員やパートタイマーなどの有期雇用労働者が、契約の更新を期待していたにもかかわらず、合理的な理由なく契約を終了(雇止め)されたとして、その無効を主張するケース。
労働条件・賃金に関する紛争
労働契約の内容や労働条件の変更、特に賃金に関することで意見が対立するケースです。
- 賃金の引下げ: 会社が一方的に給与や手当を減額したり、労働条件を不利益に変更したりしたことに労働者が納得できないケース。
- 残業代(割増賃金)の未払い: サービス残業をさせられたにもかかわらず、時間外労働・休日労働・深夜労働に対する割増賃金が支払われていないケース。
- 退職金の支払い: 退職時に退職金が支払われなかった、または計算方法に誤りがあるとして支払いを求めるケース。
職場のハラスメント(いじめ・嫌がらせ)に関する紛争
職場での人間関係や環境に起因する紛争です。
- パワーハラスメント(パワハラ): 上司や同僚から業務の適正な範囲を超えた精神的・身体的な苦痛を与えるような言動を受け、精神疾患を発症したとして、会社や加害者に対して損害賠償を求めるケース。
- セクシュアルハラスメント(セクハラ): 職場での性的な言動により、労働環境が害されたとして、適切な対応や損害賠償を求めるケース。
その他の紛争
上記以外にも、以下のような労働関係に関する様々な紛争が含まれます。
- 配置転換・出向: 会社からの配置転換命令や出向命令について、業務上の必要性がなく不当であるとして拒否したり、撤回を求めたりするケース。
- 退職勧奨: 会社から執拗に退職を促され(退職強要)、精神的な苦痛を感じたとして慰謝料を求めるケース。
- 募集・採用: 採用内定が不当に取り消されたとして損害賠償を求めるケース(労働契約の成立前だが、個別労働紛争に含まれる)。
紛争解決のための主な制度
これらの個別労働紛争を解決するための制度として、日本では主に以下の3つの手続きが設けられています。
- 都道府県労働局の助言・指導:都道府県労働局長が、紛争当事者に対して問題解決の方向性を示す助言や、法的な観点から改善を促す指導を行います。
- あっせん:都道府県労働局の紛争調整委員会などが中立公正な立場から、当事者間の話し合いを仲介し、合意による解決を目指す手続きです。非公開・無料で利用できるのが特徴です。
- 労働審判:裁判所で行われる手続きで、原則として3回以内の期日で迅速に紛争解決を図ります。裁判官と労働関係の専門家(労働審判員)が関与し、調停を試み、調停が成立しない場合は審判(判断)が下されます。
これらの制度を利用する前に、当事者同士で自主的な話し合い(任意交渉)による解決を図ることがまず求められます。