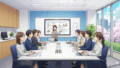労働施策総合推進法とは
労働施策総合推進法(正式名称:労働政策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律)は、労働者がその能力を有効に発揮し、充実した職業生活を送ることができる社会の実現を目指す法律です。
少子高齢化や働き方の多様化といった社会の変化に対応し、雇用環境の整備や多様な人材の活躍促進、ハラスメント防止など、幅広い労働施策を総合的に推進することを目的としています。特に2019年以降の改正では、職場におけるパワーハラスメント防止対策が事業主に義務付けられたことから、「パワハラ防止法」とも呼ばれています。
この法律は、国、地方公共団体、事業主、労働者それぞれが果たすべき役割を定め、有機的な連携を図りながら、総合的な労働施策を展開するための基本となる法律です。
主要な項目
労働施策総合推進法の主要な項目から、特に重要性の高いものを解説します。
職場におけるハラスメント防止措置の義務化(パワハラ防止法の柱)
この法律の最も注目される改正点は、職場におけるパワーハラスメント(パワハラ)の防止措置を事業主に義務付けたことです。これにより、大企業は2020年6月、中小企業は2022年4月から措置の実施が義務化されました。
具体的には、事業主に対して以下の措置が求められます。
- 事業主の方針等の明確化と周知・啓発: パワハラを行ってはならない旨の方針を明確化し、就業規則等に規定して労働者に周知・啓発すること。
- 相談に応じ、適切に対応するための体制の整備: 相談窓口を設け、相談内容や状況に応じ、適切に対応できる体制を整備すること。
- 事後の迅速かつ適切な対応: 事実関係を迅速かつ正確に確認し、パワハラが認められた場合は行為者・被害者双方に対して適切な措置を講じ、再発防止策を講じること。
- プライバシー保護と不利益な取扱いの禁止: 相談者や行為者等のプライバシーを保護し、相談や事実確認への協力等を理由とした不利益な取扱いをしてはならないこと。
この義務化は、ハラスメントを許さない職場環境の整備を企業に強く促し、労働者の職業生活の充実と安全を守る上で極めて重要な役割を果たしています。なお、セクシュアルハラスメントや妊娠・出産・育児休業等に関するハラスメント対策は、別の法律(男女雇用機会均等法など)で既に義務付けられていますが、労働施策総合推進法はこれらと並行して、全てのハラスメント問題解決に向けた総合的な施策を充実させることを目的としています。
年齢に関わりなく均等な機会の確保
この法律では、労働者の募集及び採用について、年齢にかかわりなく均等な機会を与えることを基本理念としています。
具体的には、原則として事業主に対し、労働者の募集及び採用に当たって年齢制限を設けることを禁止しています(雇用対策法時代から規定)。これは、労働者の能力や経験にかかわらず、年齢のみを理由として働く機会を奪うことを防ぎ、高齢者を含む意欲ある人々の就業を促進することを目的としています。
ただし、例外規定も設けられています。例えば、定年年齢を上限とする場合、長期勤続によるキャリア形成を図る目的で若年者を募集する場合、芸術・芸能分野など特定の年齢層の労働者が不可欠な場合など、合理的な理由がある場合に限り、例外的に年齢制限が認められています。
この項目は、少子高齢化が進む日本において、高年齢者の雇用機会を確保し、多様な人材がその能力を最大限に発揮できるような社会構造へ転換するための基本的な枠組みを提供しており、「生涯現役社会」の実現に向けた重要な施策の一つです。また、募集・採用時の年齢制限の禁止は、事業主が求職者の能力・適性に基づいて公正な採用を行うよう促し、より開かれた労働市場を形成することに寄与しています。
中途採用比率の公表
2022年10月1日以降、常時雇用する労働者が301人以上の大企業に対し、中途採用の比率を公表することが義務付けられました。
これは、新卒一括採用中心の従来の雇用慣行を見直し、中途採用をより積極的に行うことを促すための施策です。労働者のキャリア形成の多様化、労働移動の円滑化を促進し、企業が多様な経験やスキルを持つ人材を受け入れることで、労働生産性の向上やイノベーションの創出を期待するものです。
公表義務の対象となる事業主は、直近の3事業年度の各年度について、「採用した労働者に占める中途採用労働者の割合」を公表しなければなりません。公表は、企業のウェブサイトなど、求職者が容易に閲覧できる方法で行う必要があります。
この情報は、求職者が企業を比較検討する上での判断材料となるほか、企業側にも中途採用の重要性を再認識させ、組織の活性化を図る契機となります。この施策は、働く個人にとっても、転職やキャリアチェンジの選択肢を広げ、より柔軟な働き方を可能にするための労働施策の方向性を示すものと言えます。
労働施策総合推進法は、働き方の多様化や社会の変化に対応するため、ハラスメント対策や女性活躍推進など、労働政策の重要な柱を担っています。先の解説に加え、特に近年法改正で義務化・強化された以下の3つの主要な項目について解説します。
カスタマーハラスメント(カスハラ)への対応義務化
近年深刻な社会問題となっているカスタマーハラスメント(カスハラ)に対し、改正労働施策総合推進法(2025年通常国会で成立、公布から1年6ヶ月以内の政令で定める日に施行予定)により、事業主による防止措置が義務付けられました。
カスハラとは、顧客、取引先、施設の利用者など事業に関係を有する者の言動であって、社会通念上許容される範囲を超えたものにより、労働者の就業環境が害されることを指します。これには、暴行・脅迫、土下座の要求、執拗な言動、差別的な言動などが含まれます。
事業主に義務付けられる措置は、職場におけるパワハラ対策と同様に、以下のものが想定されています。
- 事業主の方針等の明確化と周知・啓発:カスハラは許されない行為であることなどの企業方針を明確にし、労働者や顧客等に対して周知・啓発すること。
- 相談に応じ、適切に対応するための体制の整備:相談窓口を設け、適切な相談対応と事後の対応ができる体制を整備すること。
- 事後の迅速かつ適切な対応:実際にカスハラが発生した場合、事実関係の確認、被害者への配慮措置(メンタルヘルス対策など)、行為者への対応、再発防止策などを講じること。
- プライバシー保護と不利益な取扱いの禁止:相談者や事実確認への協力者に対するプライバシー保護と、不利益な取り扱いを禁止すること。
この改正は、労働者を外部からの不当な言動から守り、安全で安心できる就業環境を確保するために、企業の責任を明確にするものです。
求職者に対するセクシュアルハラスメント防止措置の義務化
求職活動中の学生や転職希望者、インターンシップ生などが、採用面接やインターン中に企業側(事業主や労働者)から受けるセクシュアルハラスメント(就活セクハラ)も、改正労働施策総合推進法(カスハラ対策と同様の時期に施行予定)により、防止措置が事業主に義務付けられました。
これまでは、セクハラ防止措置の義務は「雇用する労働者」が対象でしたが、求職者に対するセクハラが深刻な問題となっていることを受け、法的な対策が強化されました。求職者は、採用という立場上の弱みからハラスメントを拒否しにくく、被害を受けやすい状況にあります。
事業主に義務付けられる措置は、雇用する労働者に対するセクハラ対策(男女雇用機会均等法)に準じたもので、具体的には以下のものが想定されます。
- 事業主の方針等の明確化と周知・啓発:求職者に対するセクハラは許されない行為である旨を明確化し、労働者に周知・啓発すること(面談等を行う際のルール作りなど)。
- 相談体制の整備と周知:求職者が安心して相談できる窓口や体制を整備し、その存在を周知すること。
- 事後の迅速かつ適切な対応:相談があった場合の迅速な事実確認と、被害者への謝罪や再発防止に向けた措置を講じること。
この改正は、ハラスメントを理由に就職機会を奪われることがないよう、公正な採用活動の確保と、求職者の人権尊重を目的としており、企業に対し採用活動における意識改革と管理体制の強化を求めています。
女性の職業生活における活躍推進(情報公表の拡大)
労働施策総合推進法は、その関連法である女性の職業生活における活躍の推進に関する法律(女性活躍推進法)の改正と連携し、女性の活躍をさらに推し進めるための施策を強化しています。
特に重要な改正点(2023年4月施行)は、女性活躍に関する企業の情報公表義務の拡大です。
- 対象企業の拡大: 従来の「常時雇用する労働者が301人以上の大企業」に加え、101人以上300人以下の企業にも、女性活躍に関する情報の公表が義務付けられました(努力義務であった企業の一部が義務化)。
- 公表項目の追加・強化: 義務付けられる公表項目に、新たに男女間の賃金差異(男女間賃金の差)と女性管理職比率が加わりました(101人以上の企業)。
これらの情報は、企業のウェブサイトなど外部から容易にアクセスできる形で公表することが求められます。
この措置は、女性の参画状況や待遇について客観的な情報を公開することで、企業に対して男女間格差の是正を促すとともに、求職者や投資家などが企業の取り組みを比較・評価できるようにし、市場原理を活用して女性活躍を加速させることを目的としています。また、法律の有効期限も10年間延長され、長期的な女性活躍の推進を国家戦略として位置付けています。
なぜパワハラ防止法と呼ばれているか
労働施策総合推進法が「パワハラ防止法」という別名で広く呼ばれるようになったのは、2019年の法改正で「職場におけるパワーハラスメント防止のための措置」が、日本の法律で初めて事業主に義務付けられたという、その社会的なインパクトの大きさにあります。
「パワハラ防止法」と呼ばれたきっかけ
労働施策総合推進法が幅広い労働施策を扱う法律であるにもかかわらず、「パワハラ防止法」という別名で定着したのは、以下の理由からです。
- 法的な義務化の画期性: 2019年以前、職場におけるパワーハラスメントは社会問題化していましたが、その防止策は法律で明確に義務付けられていませんでした。この改正により、パワハラの定義が法律上明確にされ、企業が防止措置を講じることが初めて法的な義務となった点は、極めて画期的でした。
- 社会的な関心の高さ: パワーハラスメントは、多くの労働者にとって身近で深刻な問題であり、この法改正はメディアで大きく取り上げられ、国民の関心を集めました。法律の正式名称(労働政策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律)が長すぎることもあり、この改正の核心部分を表す「パワハラ防止法」という通称が広く浸透しました。
- 対策の緊急性・重要性: 従来のセクシュアルハラスメントやマタニティハラスメント対策に加えて、パワハラが法制化されたことで、企業にとって喫緊の対応が必要な重要課題となりました。法律の通称が、その主要な改正目的を端的に示すものとして用いられたと言えます。
厚生労働省の扱い
厚生労働省は、法律の正式名称や略称(労働施策総合推進法)を用いることが基本ですが、国民や事業主への周知・啓発を行う際には、「パワハラ防止法」という通称を積極的に使用・併記しています。
- 併用による周知徹底: 厚生労働省が作成するパンフレットやリーフレット、ウェブサイトなどでは、「労働施策総合推進法(パワハラ防止法)」といった形で、正式名称や略称の後に通称を括弧書きで併記するケースが多く見られます。
- 政策のメッセージ性: これは、法律の複雑な内容よりも、「職場でのパワハラ対策が義務化された」という最も重要なメッセージを、対象者に迅速かつ明確に伝えるための広報戦略です。
したがって、厚生労働省は「パワハラ防止法」を正式な法律名としては使用しませんが、法改正の目的と企業に求められる対応を周知する目的で、この通称を認識し、活用しています。