 退職・解雇
退職・解雇 退職する従業員が秘密保持誓約書の提出を拒否したら?
退職時に従業員から秘密保持誓約書の提出を拒否された場合、会社が取り得る対抗策や措置について説明します。法的保護の根拠の確認退職時の誓約書は、従業員に改めて秘密保持義務を認識させるためのものですが、提出を拒否されても、以下の根拠で営業秘密を保...
 退職・解雇
退職・解雇  社員研修・自己啓発
社員研修・自己啓発  会社規程
会社規程 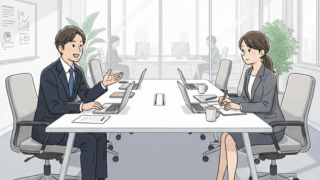 採用
採用  個人情報保護
個人情報保護 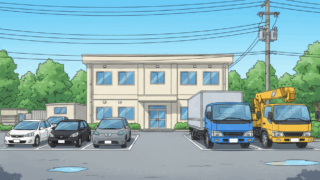 安全運転
安全運転  メンタルヘルスケア
メンタルヘルスケア 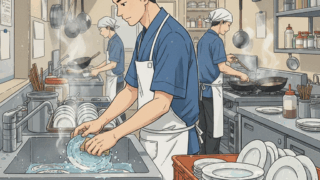 パート・有期雇用
パート・有期雇用  社員研修・自己啓発
社員研修・自己啓発  社員研修・自己啓発
社員研修・自己啓発